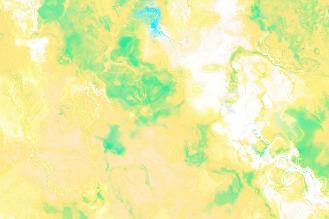
―…まずい…。
ここは鈴城宮家のある火の国北端部―…その名も『鈴城村』。村自体は木の葉よりも大きく、多くの商人や一般人がかなり豊かに生活している。その資金源は言わずもがな、だ。そこで旅人に扮して調査を進めていたが、今の目の前に広がるのはドス黒い水の塊…敵のモノもあるが、前に倒れる見慣れた銀の動物面をした暗部のそれの方が多いだろう。
事の始まりは数分前ー…村近くの森で激しくぶつかり合う3つのチャクラを感じた。しかし今は村に潜入している身、なるべくなら面倒事とは避けたい。だがもしこれがナルトやシカマルのものだったらと考えると首を突っ込まずにはいられず、つい影分身を送ってしまった。結果二人のものではないと判明したものの、今にも暗部の命の灯はどんどん消え失せようとしている。
『、アイツのチャクラ無くなってきてるぞ』
「わかってる…仕方ない。カカシさんもアスマさんもいないんだから、淀は絶対出てこないでよ!」
『さぁな、お前が上手く制御しろ』
ニヤニヤ笑う彼には小さく舌打ちをすると、影分身と入れ替わり本体で藍色のフードをたなびかせ、敵の前へと駆けだした。
…何とか意識を保っていた暗部に姿を見られていたとは知らずに…。
十三.月の舞姫 Ⅲ
「おいナルト、聞いたか、あの話」
「あ?」
猛獅子姿のナルトは、総隊長と副隊長専用の部屋で機嫌が悪そうにシカマルの呼びかけに応えた。ナルトはここ数日、ずっと不機嫌だ。理由は単純明快、数日前の家に扉に貼られていた
【しばらく夜は修行で家にいません。昼も任務で滅多にいません!淋しがらないでね!】
という紙のせい。全然淋しくなんかないが、数日姿を見ないだけでこんなにも不満になる。そんなナルトの様子にシカマルは苦笑いを浮かべながら話を続けた。
「あ?じゃねーよ。昨日火の国北部に送った暗部隊員の話だ」
「あー、相変わらずの鈴城宮家な。現場着く前に交戦になったやつか」
「あぁ。二人のうち一人は未だに意識不明、一人は重傷だが意識は戻った」
「ふーん…で、何か言ってんのか、そいつ」
「あぁ。でもよくわかんねぇんだよ」
里一番のIQを持つシカマルでさえもよくわからない話とは、一体何なんだろうか。そのシカマルの話に少し興味を持ったナルトは、話の続きを促した。
「隊員が半分意識を飛ばしつつ死を覚悟した時、突然目の前に藍色のマントを身に纏ったヤツが現れ、戦い始めた。ヤツは左足にかなり大きな怪我を負ったらしいが、最終的には元々こちらとやりあっていた鈴城宮家の暗殺部隊を倒したらしい」
「暗部内に今怪我負ってるやつは、報告書見た限りではいねぇな。それに藍色のマント…木の葉の暗部じゃねぇ」
「あぁ。だが藍色のマントなんか他里でも聞いたことがねぇ」
「なるほど」
「その暗部隊員も、敵か味方かわからねぇそいつに気を許すわけにはいかねぇ。だから何とかバレねぇように気を保とうとしたらしいが、最終的にはそいつに気付かれて手刀を受け、意識を飛ばした…」
シカマルは手刀を振り下ろす動作をして、その時のイメージを膨らませた。それを見ていたナルトはうん、と頷くと、シカマルに問いかける。
「ってことは結局木の葉の敵なのか、その藍色のヤツは?」
「だがその後、その二人は怪我もそのままの状態で、木の葉の入り口に送り届けてる」
「…意味わかんねぇな。味方ならその場で軽く応急処置を施すはずだ。ましてはそれだけの実力のあるやつなら医療忍術の一つや二つ出来そうな感じだよな」
「あぁ。でもそいつは何の応急処置もせず、ただ無言で門番に明け渡しただけらしい。そして最も意味わかんねぇのが、敵が発したという『月の舞姫』と門番が見た『銀の豹面』の二つ」
人差し指と中指を立ててナルトに説明するシカマル。銀の動物柄の面を被るのは木の葉の暗部ならではのこと。他里では聞いたことがない。それに全身を単色のマントで覆うのも同じだ…ただ色は違うが。そして気になるのが『月の舞姫』という言葉。
「何なんだ、その『月の舞姫』ってのは…」
「何でもその藍色のヤツが敵の目の前に現れた時、敵が驚いたようにそう口走ったらしい。そしてこうも言ったってよ、『姫自ら現れるとはな…』ってよ…」
「姫ってことは女なのか?」
「さぁ、声は聞いてねぇらしい」
「わけわかんねぇ」
「だろ?オレも何が何だかさっぱりだ」
「…とりあえず、そいつについては今後も何か情報を仕入れてくれ。敵か味方かわかんねぇうちは用心するに越したことねぇ」
「あいよ」
『銀の豹面』の『月の舞姫』…それはそれで気になるが、そんなわけのわからない忍よりも、今のナルトにとってはがいつ帰ってくるのかという問題の方が、はるかに比重が大きかった。
********
この日以降『月の舞姫』は何度となく暗部の元へと現れるようになった。それも三代目の命により鈴城宮家について調査をさせようと送った暗部の元ばかりに。危険に陥った際に助けてもらった者、怪我をした時に血止め薬を投げてよこされた者、鈴城宮家に潜入しようとして意識を飛ばされ里に返されたものもいる。ついには少しだが声を聞いた者も現れ、それにより『月の舞姫』は女ということが判明した。
その報告を受けたナルトとシカマルは余計にわからなくなる。味方らしいが、二人が任務の際は現れたことがない。鈴城宮家の調査を再開したこともあり、対象貴族の情報は元より何故か『鈴城宮家』に近付くと必ず現れるこの謎の忍についてももっと詳細を得ようと、二人はさらに暗部を任務へと送り出した。
これら話は当然三代目の耳にも入り、状況を説明してもらおうと慌ててを火影邸へ呼び出す。未だ村で潜入調査中のは影分身をよこして説明した。
「どういうことじゃ!いつの間にか暗部にまでお主の存在が知れ渡っとるではないかっ!!」
「そうなんですよ三代目様…どうしましょう…」
「『どうしましょう…』じゃないわぃ!何があったんじゃ!」
「それがですね…」
........
.....
...
が初めて暗部を助けてしまったあの日、それなりに大きな傷を左足に負い、正常に歩くことすら困難になっていた。しかも運悪く、の姿も足を引きずっている様子も、意識を保っていた暗部に見られてしまった。それに気付いて慌てて手刀で意識を飛ばさせるも時すでに遅し、目覚めた暗部はの存在を猛獅子と明虎という、が最も知られたくない相手に伝えてしまった。
そうとは知らずはその後も村で調査をしていたが、併せて三代目が鈴城宮家についての調査を暗部でも再開したことを受けて、何度か暗部の姿を目にしていた。だが鈴城村には鈴城宮家が雇った暗殺部隊でもいるのであろう、よくぶつかる姿を目にしていた。は暗部に身を置いていないため、顔も割られていない。一般人として紛れ込んでいるため今までぶつかることはなかったが、このことにより暗殺部隊の形態や戦闘スタイルも把握することが出来た。
だが一方で、この『暗殺部隊』の情報を与えてくれた、戦う同胞を見過ごすこともできない。一度助けてしまった故に自分でもどこまでサポートしていいものか分からなくなってしまった。また怪我人を放っておくことも心苦しくなり、気付いたら自分がメインで戦っていることもしばしばあるようになってしまった―…。
...
.....
.......
事の顛末を聞き、あまりにもらしいその状況に三代目は笑みを浮かべたのだが、これではあまり表舞台に立たせたくない彼女の存在が浮き彫りになってしまっている。それどころか、ナルトやシカマルに存在を知られてしまった。
「で、でもご安心くださいっ!ちゃんと私だとバレないように、猛の技は使用しておりません!」
「バカモン!自慢していうことでもないわいっ!!」
「…申し訳ございません…」
「はぁ…もういっそのことナルトに言うかのぅ。その方が今後の潜入も安全じゃ」
その言葉には目を大きくする。そして首を横に振って言った。
「それだけは止めてください!ナルトの言うことを聞かずに勝手にやっていて、大変なことになってきたから甘えるだなんて虫がよすぎます!」
「じゃがのぅ…」
「お願いします三代目様!情報もかなり得ましたし、あとは潜入して潰すだけですから!外は確かに暗殺部隊などいて面倒ですが、中はそれほど強固な守りでないことは確認できています!すべて終われば上忍としても裏暗部としても、通常任務に戻れます!」
真剣な瞳で見つめる。三代目も真剣に見つめ返す。しばしの沈黙が流れていたが、はぁ…と思いため息をつくとに語りかけた。
「本来ならすぐにでも辞めさせるのじゃが、お主の助けによって暗部の命が大勢助かっているのも事実。そして長年頭を抱えていた【鈴城宮家】についても解決するまであと少し…何が何でもやり過ごし、ヤツを潰せ!」
「御意っ!!」
『面白くなってきやがったな』
三代目と淀の言葉に、はにっこり微笑んだ。
*********
その後暗部が鈴城宮家への任務に出るたびに、『月の舞姫』は現れた。しかし俺や明虎の任務の際は現れない。気配さえ感じないのだ。今まで暗部のヤツらが伝えてきた特徴とこれまでの情報…『女』『小柄』『軽い身のこなし』『俺達二人の前には決して現れない』、さらにその舞姫が現れて以来、思い当たる人物がちょうど同じ期間『夜は修行』『昼は任務で忙しい』と言って全く会えていないという状況を踏まえ、オレは想像したくないコトを考え始めていた。
―…なら充分ありえる…勘弁してくれ…。
出会ったばかりの頃から突拍子も無い事をする彼女。今回もその一つなのか…。頭に手を待っていき天を仰いでいると視線を感じ、ふと横に視線をやる。そこには明虎がジト目で俺を見ていた。
「…なんだよ」
「お前、に『暗部入れない』って伝えたんだよな」
「あぁ」
「そん時アイツ、なんか言ってたか?」
「いや、割と普通に『わかった』って…。あん時は妙に物分かりいいなぁと思ったが…」
「…バカナルト。それは物分かりがいいからじゃねぇ。抜け穴を見つけてたからこその余裕だろうが」
「…」
オレより賢いシカマルのことだ、恐らく彼の中で『舞姫=』の方程式は完全に完成してあるのだろう。いつもならシカがそう言えば信じきる俺も、今回ばかりは彼の考えが外れていることを祈りながら一つ大きなため息をつくと、事の真意を確かめるため火影の元へと向かった。
*********
「じいちゃん、『月の舞姫』って知ってるか?」
が本格的に鈴城宮家へ潜入する前日。彼女も必要な荷物をまとめに、帰還した日。月の舞姫の情報がかなり集まってきてしまった今、三代目はそろそろナルトがここへ来ることは分かっていた。しかしの意志もある。何とかしてここを切り抜けねばならない。三代目はごくりと喉をならずと、ある作戦を試みることにした。
「何なんじゃ突然、ナルト」
「それが…じゃなくて、この姿の時はその名前で呼ぶなっつってるだろ、クソジジィ」
「口だけは一丁前に悪くなったのぅ、このガキンチョ」
「今は十六の姿だ、ガキじゃねぇ」
「見てくれの話をしてるんじゃ無い、中身の話じゃ」
「うるせー!だいたい口が悪ぃのはじぃちゃんの育て方が悪ぃんだろ」
「なんじゃ、育ててもらった恩をそうやって返す気か」
「へんっ!知らねぇよ、そんなんっ!」
「ほー、そんなこと言っていいのかのぅ?わしは別に良いんじゃぞ、ナルトが毎晩夜寝るのを怖がって泣いていた挙句に毎朝おねしょをしていたのをに話し…」
「それもじぃちゃんが悪ぃんだろ!毎晩怖い話ばっか聞かせやがって!それにそれは…って話がズレすぎじゃねぇか!!」
バンッと机をたたく音と共に、三代目の『話を逸らそう作戦』はここで閉じてしまい、内心舌打ちをした。そんな三代目の思惑など露知らず、ナルトは自分の考えている事を口にした。
「で?じぃちゃんは『月の舞姫』知ってんのか?」
「小耳に挟んだことはあるが、詳しくは知らんのぅ」
「ここ最近何度も暗部を助けてる小柄なくの一でよ、すんげぇ強いんだと。藍色のマントで身を包んでいて、銀の豹面を付けてる」
「ほー、それは不思議なヤツが現れおったのぅ」
そういってしらばっくれている間も、真剣にナルトはこっちを見てくる。そう、それはまるで真意を探ろうとしているかのように、じーーっと。三代目は小さく苦笑いを浮かべると、ごまかすように熱いお茶を啜った。
「…なぁじぃちゃん、はどこで修行してんだ?上忍の仕事はしてんだよな?」
「突然何じゃ。が恋しくなったか?」
「そんなんじゃねぇ。いいからあいつの任務は?」
「さぁのぅ…それはわしじゃのぅて受付で聞くのが筋じゃろうが」
「まぁ、本来ならな。あ、あと豹柄の面って暗部にあんのか?」
「暗部の面は動物の面、あってもおかしくはないじゃろうな」
「ふーん…」
そういうとナルトは三代目から視線を逸らす。ナルトは知っている。この人がどんな人であるのか。ナルトや里を思って言えないことは絶対に言わないし、かといってナルトを見放す人でもないということを。このままでは埒が明かない。ナルトはキッと三代目を睨むと、強めに言葉を続けた。
「じぃちゃん、正直に答えろよ」
「…」
「舞姫はだろ」
「…知らぬ」
「…もう一度言う。正直に答えろよ?『舞姫はだろ』」
「…お主はそうであって欲しいのか?」
「っんなわけねぇだろ!そうであって欲しくねぇんだっ!」
には危険な目にあって欲しくない。忍だから無理なのはわかってるけど、自分の目の届く範囲で、出来るだけ危険とは無縁の世界で笑って欲しい…。そう思うと同時に、『=舞姫』と考えると胸が痛くて顔が歪む。その表情に苦笑いを浮かべ、小さく「変わったのぅ、ナルト」と零した。
「聞きたいことがあるなら、直接に聞くのじゃ。わしは何も出来ん」
「…それは肯定してんのか?」
「そうとも言えるし、そうとも言えぬ」
「…くそっ!」
バンッ!という大きな音と共に扉が閉まり、ナルトは出て行った。そんな彼の様子を、苦笑いを浮かべて三代目は見送った。
―…すまぬ、あんな顔を見ては黙っておれんかった。お主のことが心配で心配で、たまらん様な顔をのぅ…。
沈みかけた優しいオレンジ色が辺りを包み、三代目は視線を窓の外に見える金色の少年に目を移す。少年は、迷いなく真っ直ぐと駆けて行った。
ナルトがの家の扉を叩くまで、あと数十秒…。