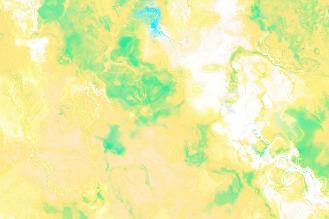
日に日に出来ることが増え、強くなってきている実感はある。その分失敗は沢山あって、前向きな私でも毎日凹んでばかりいる。
それでも毎日頑張れているのは、翡翠色の瞳をした優しい彼のおかげ。
冬獅郎は私にとって、昔も今もかけがえのない存在だー…。
Time to Shine 9
「よし、今日はここまでにするか」
「あ…ありがとうございましたぁ…」
終業時間となり、お礼の言葉と同時に私はそのまま大の字に倒れた。汗まみれの体で道場に倒れている私の視界に、汗ひとつかいていない恋次くんがひょっこり顔を出す。これが席官と新米の差か。
恋次くんは私にとっては師匠なんだし、初日にきちんと『阿散井さん』と呼んだら拒否された。頑なに『恋次でいい』という彼に、流石に呼び捨ては出来ないと訴えて『阿散井さん』呼びを続けていたら、たった数回で鉄拳がお見舞いされた。『恋次くん』もどう見ても年上なので何とも呼びにくさはあるものの、もう一度あの痛みを味わうのは御免なので黙って従っている。
「おい、生きてるか?」
「…何とか…」
十一番隊に配属になり二週間。更木隊長との『遊び』という名の実力テストまでも、あと二週間。あれ以来、毎日恋次くんがそれはもう吐くほどの修行をつけてくれている。途中までは数えていたが、何度怪我で四番隊にお世話になり何度意識を飛ばしたか分からなくなったので、数えることを放棄した。
私は他隊の隊員なのに、心配症な冬獅郎は時間を見つけては様子を見に来てくれて、やれ怪我はないか身体は問題ないか心配してくれる。その優しさが嬉しくてニコニコと頷くと、冬獅郎の眉間の皺がほぐれていつも小さく微笑んでくれる(その度にいつも周りが騒ついたけど…何でだろう?)。そして冬獅郎と、二日酔いじゃなくて寝坊もしない日は乱菊さんも、私の朝の自主鍛錬に付き合ってくれる。そんなこともあって、私の修行はすこぶる順調に進んでいた。
「それにしても…」
「?」
恋次くんは言葉を切り、相変わらず息切れしながら寝転ぶ私の隣に座って見下ろす。
「お前、死神の素質あんだな。始解までマジでもう少しじゃねーか。鬼道はてんで駄目だけど」
「鬼道に関しては恋次くんの教え方では…」
「なんか言ったか?」
「…なんでもないデス」
眉間をピクピクさせながら言う恋次くんをこれ以上怒らせるのは怖いので、この辺で終わらせよう。
私の斬魄刀はいつもペラペラと語りかけてくるが、相変わらず肝心な名前は教えてくれない。真っ黒な服を着た男性は冷静に『お前はもう知ってるはずだ、バカ』とバカにしてくる始末だ。この調子で二週間経っていて正直ムカついてきている気持ちを何とか押し留め、私は道場の天井を見つめた。
「、帰るぞ」
恋次くんの隣で相変わらず天井を見つめながら雑談していると、ガラリと言う音とともに凛とした声が道場に響く。この声の主はいつも私を心配して、終業と同時に迎えにきてくれる。
「お疲れ様、冬獅郎ー…」
「…あーあ、今日も派手にやられたみたいだな。名前は聞けたか?」
「まだ。何なのさ、このダンディなおじ様!」
意地悪過ぎて腹立つよ!と私の隣にある刀を睨むと、また一方的に語りかけてくる。落ち着いて話しかけてくる割にぐさぐさ刺さることを言ってきて、私はついに「うるさーい!」と大声を出す。すると冬獅郎が噴き出し、寝転ぶ私の隣に腰掛けた。
「まぁ始解まであと少しの新人ってだけで、充分凄いからな。うちの隊の奴らも、お前のこと知ってたぞ」
「みんな凄いって言ってくれるけど、蓮もあと少しだし、そんなに凄さが分からないよ」
上体を起こし、終業時間になったのにまだ稽古を続けている蓮と一角さん、そしていつの間にか移動していた恋次くんを見る。そう、蓮も始解まであと少しのところまで来ているらしい。それに男性ということもあり、基礎体力も私と全然違って、まだ動けている。それがかなり羨ましい。
「…早く始解出来るようになって、冬獅郎の側で働きたいな」
心の内を小さく零すと、冬獅郎は頑張れ、と頭を撫でてくれた。
********
「シロちゃん、こんなところにいた!」
「…うるせーのが帰って来た」
「??」
蓮の稽古も終わり帰ろうと立ち上がると同時に突然響き渡ったソプラノに、私は振り返る。そこには黒髪を一つに纏めた女性が笑顔で立っていて、迷いなく冬獅郎の元へ駆け寄った。
「シロちゃん、ただいま!」
「日番谷隊長だっての。怪我はねーか?」
「うん、大丈夫。シロちゃんは?怪我してない?」
「特に戦うこともなかったし、してねーよ」
そっか、と優しく微笑む女性の雰囲気はとても柔らかくて、この数分だけで彼女は冬獅郎のことがとても大事なんだろうと感じた。それにしてもー…シロちゃんとは。猫じゃなくて、冬獅郎もシロちゃんだったのか。なんかごめん。
そんなことを考えていると、冬獅郎は「あぁ、そうか」と言い、紹介してくれた。
「コイツ、幼馴染の雛森桃」
「はじめまして。五番隊副隊長の雛森桃です」
「黒崎です。よろしくお願いします」
雛森さんは「黒崎…」と一言いうと、ジロジロ見られた。見られるというか、先程の冬獅郎への優しい眼差しから一変、睨まれてる気がする…。私、何かしてしまっただろうか…。対応に困り小首を傾げると、雛森さんは突然ニコッと笑みを浮かべ、冬獅郎に振り向いて言った。
「で、シロちゃん、約束だよ!ご飯行こう!」
「…約束なんかしたか?」
「えー!私が任務行く前に『帰ってきたら奢りでご飯』って話したでしょ!」
ほんとシロちゃんはいつまで経っても忘れっぽいから、私がしっかりしないと!と言うと、少し怒ったように頬を膨らませる雛森さん。その姿は同性から見ても可愛らしく、何より『副隊長』と言うことは強さも兼ね備えている証拠。才色兼備とは正しく彼女のことだな、と思った。冬獅郎は私を見ると、少し考え口を開いた。
「、お前も行くか?」
「え?いい、いい!いってらっしゃい!」
前から約束していたようだし、隊長副隊長の席にはさすがに行きづらい。私は慌てて首を横に振ると、冬獅郎は申し訳なさそうに言った。
「そしたらお前は、先執務室行ってろ。開いてるしシロもいる」
「いやいや、今日は冬獅郎もいないし流石に自分の部屋帰るよ」
「いいから。終わったら行くから、シロと待ってろ」
「…分かった。ありが…」
とう、と私のお礼も言い終わらぬうちに雛森さんは「ほら、行くよ!」と彼の腕を引き、道場から出て行った。…やはり私、知らないうちに彼女に何かしただろうか?バタンと勢い良く閉じられた扉を前に、私は首を傾げる事しか出来なかった。
********
誰もいない執務室の扉を開けると、中はシロを思ってか明かりがついていた。そして足元には真っ白なシロが駆け寄るので、私は笑顔で顎の下をゴロゴロする。ふと冬獅郎の席を見ると、仕事を途中で切り上げて迎えにきてくれたのか、やりかけの書類や筆が置きっぱなしになっていて申し訳なく感じた。
初めて酔っ払ったあの日、私は本当に久しぶりに安眠することが出来た。この半年、いつ襲われるかもわからない生活で充分に眠ることができず、睡眠はいつも蓮と交代でとっていた。眠ったら眠ったで、いつも追われ追い詰められ殺される夢ばかり見て、正直眠ることが怖くなっていた。なので冬獅郎と初めてここに来た日、私は一人で寝ることへの不安と悪夢が怖くて、彼の仕事場まで行くと甘えてしまった。
すると驚くことに、その日は悪夢も見ず安心しきって眠ることが出来た。あんなに深く眠れたのは現世にいた時以来。だが、仕事に戻りたいはずの冬獅郎の手を握りしめ、私はソファで横になっていたのに彼は座らせた状態で一緒に眠りこけてしまった事実に目覚めて気付き、それはもう土下座して謝った。すると冬獅郎は、土下座する私の頭にポンっと手を置き「怖いのなんか来なかったろ」と笑ってくれて、その笑顔と優しさに胸がキュッとしたことは内緒だ。
その次の日は自室で眠ったがやはり悪夢にうなされ、それが原因で翌日の修行で恋次くんの木刀で思いっきり肩を殴られるという、あり得ない怪我をしてしまった。一瞬にして真っ青になった恋次くんに担がれ即座に花太郎さんが治療してくれてことなきを得たが、それ以来、冬獅郎は終業後は必ず執務室まで連れてきてくれて、仕事をする冬獅郎を横目に眠くなるまでソファに居させてくれるようになった。
人が近くにいる安心感からか、あるいは冬獅郎の側だからか…ここでは気付くとウトウトしてしまう。そのまま眠ってしまい、目が覚めたら運んでくれたのか一人自室の布団で寝ていたり、あるいは冬獅郎と執務室のソファでそのまま眠っていたりしている。冬獅郎だって疲れているに違いないのに、これじゃダメだと謝り断っても「俺がしたいようにしてるだけだから気にすんな」と笑ってくれる。そんな冬獅郎の優しさに甘え、毎日彼と過ごすこの時間が、私にとって癒しの時間になっていた。
シロと戯れながらこの部屋の主人の帰りを待つ。一人でここにいても眠くならないのだから、やはり『冬獅郎の側』という一番の安心感が私の眠りの材料となっているんだろうと気付いた。
しばらくすると静かな空間が気持ちいいのか、シロは私の膝の上で眠り始めた。膝に感じる温もりを感じながら、私は苦手な鬼道についての書物を広げる。少し寂しさを感じて足首を意識的に動かすと、翡翠色の石の感触を感じる。会えたけどまだ返さないのは、私のワガママ。同じ色の瞳をした彼に会えることを信じてずっと御守りがわりにしていたこの子を、私はなかなか手放せずにいた。今度もうちょっと貸しててって…次は『十番隊に入るまでの願掛けで貸して』って言ってみよう、そう決めていた。
........
.....
...
静かに書物を読んでいると扉が開く音が響き、冬獅郎が帰って来たのかと目を向ける。しかしそこには冬獅郎ではなく、彼とのご飯を終えたのか雛森さんが立っていた。
「こんばんは、ちゃん」
「…こんばんは」
想定外の人物の登場に少なからず驚き、返事が遅れてしまった。あれ、彼女は五番隊って言っていたはず…冬獅郎もいないけど、ここに何か用なのかな?彼女はいろいろと考えて首を傾げている私の近くに音もなく近寄ると、私の膝上で気持ちよさそうに眠るシロを見て言った。
「シロ、ちゃんに懐いてるんだね」
「そうみたいですね」
「この子、初めて会う人には警戒するのに…」
「…」
それは現世で会ったことあるからです、とも言えず、私は苦笑いを浮かべてシロの頭をそっと撫でる。定期的に冬獅郎や乱菊さんがブラシをするので、撫で心地はいつも最高だ。初めてシロと出逢った時の姿は思い出すだけで胸が苦しくなるが、こうやって再び会えて本当に良かった。そんなことを考えていると、ソファに腰掛ける私を見下ろす形で雛森さんが小さく言った。
「警戒してないのって、現世で関わりがあったからだよね」
「?!」
「私、知ってるの。ちゃん、シロちゃんともシロとも、現世からの知り合いなんだよね」
うちの隊長には言っちゃったけど、藍染隊長含めてシロちゃんに口止めされたから公言しないよ、と雛森さんは笑った。さすが冬獅郎、口止めしてくれていた。私は安心から小さく息をついた。雛森さんは微笑みながら私の隣に腰掛ける。そして私を見て言った。
「シロちゃんと仲良してくれて、ありがとう」
「いえ…」
「私とシロちゃんは幼馴染で、小さい頃からずっと一緒なの。だからどうしても、シロちゃんのことがいろいろと心配になっちゃうんだ」
そこまで言うと、雛森さんは言葉を切る。そして真剣な顔で私に言った。
「シロちゃんのことは、私が一番よく知ってるの」
「…」
「ちゃん、十一番隊だよね?」
「はい」
「シロちゃんは優しくて何も言わないだろうから、私から言うね」
そういうと、彼女は私の目を見つめて小さく微笑みながら言葉を続けた。
「シロちゃんはちゃん一人の存在じゃなく、護廷十三隊十番隊の隊長なの。だから、シロちゃんに無駄な負担はかけないで」
どう言う意味かわかるよね?と言われ、私はそっと彼の机を一瞥し、小さく頷く。
彼女の言っていることは間違っていない。朝の鍛錬に付き合ってくれて、日中は手が空いたら様子を見に来てくれて、夕方は仕事が途中でも迎えに来てくれて、さらに夜は眠くなるまで一緒にいてくれる…そんな優しさにすっかり甘えてしまっていた。冬獅郎は私よりも数百倍忙しいのに私ばかり満たされていて、今の状況は彼にとって全然良くないはずだ。何で言われるまで気付かなかったんだろう。
私はキュッと唇を噛み締めると、眠っているシロをそっと抱き上げ雛森さんに預けた。甘えすぎちゃダメだ、何のためにここにきたんだ。しっかりしろ、私。
「私、帰ります」
「…シロちゃんには私から言っておくね」
「はい、ありがとうございます」
笑顔で手を振る雛森さんにお辞儀をし、私は執務室を去った。「私、間違ったこと言ってないもん…」と拗ねるかのように小さく零された彼女の声は、私の耳には届かなかった。