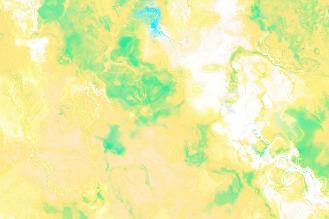
この状況に、俺はいつも以上に眉間にシワを寄せている。
右には酒瓶片手ににこにこ笑っている松本。そして正面から俺にギュッと抱きついているのは、すっかり出来上がった。
―…には今後絶対、酒は飲ませないことに決めた。
Time to Shine 8
「とーしろぉー!私寂しかったんだよぉー!」
「あー、分かった分かった」
「いろんなとこ、ずーーっと探したんだよぉー!」
「それはすまなかったな」
「本当だよ、森の中とかぁ、穴の中とかぁー」
「…俺はクマか」
その返しには俺の肩に手を置き顔をじっと見てくると、「とーしろぐまぁぁ!」と言いながら爆笑した。そして次には突然電池が切れたかのように静かになり、いそいそと抱きついてくる。肩口にある彼女の顔をのぞけば、頬を染めて眠そうに目をこする姿が可愛らしくて、思わずそっと背に手を回し小さくたたく。すると自分の背に回された腕にキュッと力が込められ、微笑んだ。なんだこの可愛い生き物は…とは言え、相手は酔っ払い。今後誰にでもこんな風にされたらと思うと、たまったもんじゃない。
「…松本、今後絶対コイツに酒を飲ますなよ」
「えー、聞こえませんよー?ほら、水飲みなさい!」
「んー…ありらとぉ、乱菊さん…」
眠気眼で差し出されたグラスに口をつける。だが一口飲むと不満気に「これちがう〜」と言ってグラスを俺に押しやり、再び抱き付いて舟を漕ぐ。違うってまさか…俺はグラスの匂いを嗅ぎ、グラスを差し出した張本人を睨む。
「おい、これ日本酒じゃねーか!酒をグラスいっぱいに注ぐな、バカ!」
「…ちぇっ、バレたか!」
松本は悪びれもなくグラスを受け取ると一気に飲み干し、ニヤリと笑う。コイツがこの顔をする時は大体ロクなことがない。俺は眉間のシワが更に増えた気がした。
********
「それにしても、やっぱり可愛いですねぇ」
「…酔っ払いに可愛いもあるか」
「でもほら、酔って本来の甘えんぼが戻ってきた感じがします」
昨日はあんなだったし、今日は朝から扱かれてたみたいですしね、と言うと、松本は俺の肩口で寝息を立てるを優しく撫でた。
「安心してる証拠ですね」
「…そうだな」
この半年、こうやって気が抜けることは無かったかもしれない。全身で甘えることも出来ず、必死に生き抜いたんだろう。そう思うと耳元で間抜けな音を奏でている小さな寝息が、愛しく感じた。本当に無事で良かった…。
「…さてと。も寝ちゃったし、そろそろお開きとしますか!」
「そうだな」
「では、私これから恋次達と合流する約束なんで、お願いしますね!」
「は?!俺これから仕事にもど…」
「送り狼にならないでくださいねー!じゃっ!」
ごちそーさまでした!と言うことだけ言うと、松本は我先にと去って行った。三人分の伝票と、俺の腕の中でスヤスヤ気持ちよさそうに眠るを残して…。
........
.....
...
眠るをおぶって、店を出る。悔しいことに彼女の方が背が高いが、おぶるくらい何ともない。俺は彼女を抱え直すついでに小さく揺すり、声を掛ける。
「おい、お前寮だろ?部屋どこだ?」
「んー…とーしろはおうち帰るの?」
「いや、今日中に片付けたいものがあるから、執務室に戻る」
「ふーん…」
俺の答えに何やら考えることでもあるのだろうか、それきり黙ってしまった。とりあえず寮の方角へ歩けばそのうち言うだろうと、俺は歩を進めた。
静かな夜道に俺の草履の音だけが響く。少しずつ秋に入れ替わろうとしている空気は少し冷たくて、空には星が輝いている。夜の散歩が気持ちいい季節になってきたな、と思いながらゆっくり歩いていると、背中から小さく俺を呼ぶ声がした。
「どうした?」
「…とーしろ、執務室、私も行っちゃダメ?」
「は?お前は部屋に帰れ。疲れてんだろ」
「疲れてないもん」
そう言うと、は肩に顔をうずめて首をふる。「疲れてないー」と言いながら首筋に擦り寄る感触に少しのくすぐったさを感じる上に、素直に甘える様子に小さく笑った。そしてそのままの体勢で、拗ねたように言葉を続けた。
「どーしても一緒に行っちゃダメ?」
「…来てどーすんだよ」
「邪魔しないよ、静かにしてる」
「ね?」という言葉と同時にギュッとしがみつく力が強くなる。その体からは『梃子でも離れないぞ!』という執念に近いものを感じる。何考えてんだ、この酔っ払いは…。だが部屋に連れて帰そうにも部屋がわからない。早く休ませてやりたい気持ちもあるし、正直こうも甘えられて悪い気がしないのも事実。
今日は執務室のソファに寝かせるか。そう決めると俺は再び彼女を抱え直し、執務室へ向かうことにした。
********
執務室の扉を開くと、クッションの上で丸まっていたシロが一声鳴き、軽やかに近寄って出迎えてくれた。元々戻ってくる予定だったので、彼はここで留守番させていた。
歩いている間に再び眠ってしまったを、静かにソファに寝かせる。小さく華奢な体で、本当によく頑張った。ふと色の白い足首に目をやると自身の翡翠色の石が映えていて、小さく微笑む。そして上から隊主羽織を掛けてやる。
その様子を見ていたシロはソファに軽やかに飛び乗ると、の腹の上で丸くなった。そんな穏やかな光景に小さく笑いそのまま自席へ行こうと一歩踏み出すも、すっかり眠っていると思っていた相手に裾を軽く引かれ、足を止めた。
「起こしたか?」
「…んーん、眠りが浅くて…。ね、とーしろ」
「ん?」
「ここならぐっすり寝ちゃっても、虚来ない?殺される夢、見ない?」
その一言で彼女が何故、一人になる自身の部屋に戻りたがらなかったのか理解した。そうだ、昨晩は俺がずっといたが、その前までは佐伯と二人、ずっと外で過ごしていたんだ。それもいつ誰に襲われるか分からない状況で…。初めての場所で、一人で眠る事に不安がないはずがない。そして『殺される夢』は毎晩見てよく眠れない、と彼女は哀しそうに続けて教えてくれた。
俺は握られていた裾をそっと離させその手を握ると、その場に座り横になる彼女と目線を合わせた。は酔いも眠気も醒めたのか、綺麗な瞳で真っ直ぐ俺を見ている。
「お前を狙う虚は来ねぇし、そんな夢も見ねぇよ」
「…ほんと?寝ても誰も殺しに来ない?」
「あぁ、お前が眠るまで側にいるから、安心して寝ろ」
もし来ても俺が倒してやるし、魘されたら起こしてやるよ、とそっと頭を撫でてやると、は安心したように微笑み、頷いた。
横で目を瞑る彼女の髪を梳きながら、ふと現世にいた頃のことを思い出す。よくこうやってが寝付くまで側にいたが、今目の前にいる彼女はあの頃からは想像もつかないくらい、頬も唇も色鮮やかだ。そのことを嬉しく思う反面、これから死神として成長し生きていく彼女を、一番近くで見られないことがとても悔しい。
「」
「んー?」
「お前、死神になったら俺のこと助けてくれるって言ったよな」
「うん」
名前を呼ばれたことで再び開かれた瞳は相変わらず綺麗で、その中に俺が映るのが見えた。そこに映し出された俺は、あからさまに不満げな表情をしている。そんな俺の表情に不思議そうに首をかしげると、じっと見つめて微笑んで言った。
「違う隊になっちゃったけど、今もその気持ちに変わりないよ。私は冬獅郎を守るために死神になりたかったんだから」
まだ全然へなちょこだけど、何かあったら絶対言ってね、と言葉を続ける。こんなにもまっすぐ俺を見続けてくれているに心が潤うのと同時に、十番隊に入れる邪魔をして来た佐伯に再び怒りを覚える。頭を軽く振ることであの小憎らしい顔を脳内から追い払う俺を、は不思議そうな顔をして見ていた。
「十番隊…」
「??」
「今すぐには無理だが、必ずお前をここに入れる。それまで死ぬ気で鍛錬しとけ」
「…うん!」
「目指せ、冬獅郎直属の部下ー!」と、まるでしっぽを振るかのように喜ぶ彼女が可愛くて、思わず噴き出す。それと同時に目の前にあるオレンジ色を優しく撫でると、彼女も満足そうに受け入れ、笑った。