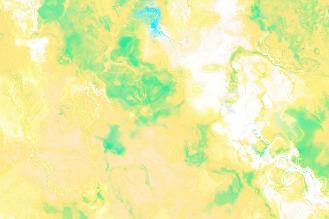
綺麗な夕焼け色に染まる執務室。
終業時刻となり隊員が帰れば「あぁ、やっと静かに仕事が出来る…」と思う時間帯。
だが今日ばかりは終業の鐘が鳴った瞬間、いつもならさっさと帰る松本も机から動かない俺も、十一番隊隊舎に乗り込んでいた。
Time to Shine 6
「っ!迎えにきたわよー!!」
十一番隊の隊舎に入るや否や、松本が大声でを呼ぶ。だが辺りを見回すも、目当てのあのオレンジ髪が見当たらない。突然の訪問に驚いたのであろう、名も知らぬ隊員が声を掛けてきた。
「松本副隊長に日番谷隊長も!一体如何されましたか?」
「アンタに用はないわよ!どこ、黒崎!」
「あぁ、新人の女なら道場で鍛錬中ですよ」
さも当たり前かのように発言した隊員の言葉に、俺も松本も目を見開く。もう鍛錬?昨日倒れたばかりなのに…?更木の野郎、何てことしやがる…!!俺も松本もまるで自隊の廊下を歩くかのようにずかずかと歩を進め、道場へ向かった。
「「っ!!」」
バンッという勢いよく開かれた扉の音と共に視界に入ったのは、今朝ぶりの件の少女。髪は整えたのか肩ほどに切りそろえられ、目を丸くしてこちらを見ている。彼女は道着を身に纏い、手には昨日佐伯が『のもの』と言っていた細かな装飾のある桃色の斬魄刀が握られている。
「ら、乱菊さんに冬獅郎?!どうしてここに?!」
「どうしてじゃないわよ!怪我はない?体調は大丈夫?!」
「だ、大丈夫です!至って元気です!」
そのままの勢いでの華奢な両肩に手を置き、激しく揺さぶる松本。その揺れに多少驚きながらも、は元気だと微笑んだ。その様子にほっと一息つくと、松本は自分の眼下にあるオレンジ髪をそっと頭を撫でる。
「全く、初日から無理しないでよ…ってあら、恋次もいたの」
たった今気付いたのか、の後ろにいた阿散井をジト目で見る。阿散井は「オレのこと、今頃気付いたんっすか」と頭を書きながら溜息をついた。
「そりゃいますよ、オレがコイツにいろいろ教えることになったんすから」
「恋次が?!教育係なんかあんたに出来る?の可愛い顔に傷つけたら許さないわよ!」
「傷付けずに教えるなんか無理に決まってんじゃないっすか!」
一ヶ月後にはうちの隊長が遊ぶって言ってんすからそれまでには何とか形にしなきゃいけないんですから!と焦ったように話す阿散井。…は?遊ぶ?更木が??それってー…
「おい、それってまさか…」
「はい、と佐伯の実力を見るために、試合形式でやり合うそうです…」
「「?!」」
「恋次くん、教えるの大雑把でなかなか習得するの大変そうだけどね」
「あぁ?!うるせーぞ、!」
が松本の胸元からひょっこり顔を出して言う。本当のことだもん、と頬を膨らます彼女は相変わらず可愛いが、たった1日で『』『恋次くん』と呼び合う姿に少しモヤっとした。それにしても更木の野郎、一ヶ月後にやり合うだと…?ふざけんな!!この件についてはあとで更木に言うとして、俺はとりあえず今日の目的である『を連れ出す』ことに向けて動き出した。
「今日はもう終わりだろ。悪いがコイツ借りるぞ」
「は、はぁ…」
「をどこに連れて行く気ですか、日番谷『十番隊』隊長?」
やけに『十番隊』や強調してくるその言葉と共に、冷たい殺気を感じ振り返る。そこには表面的には笑顔だが、間違いなく「お前他隊だろーが。出てくんな」という怒りを覚えている佐伯の姿があった。気付かなかったが、佐伯も同じ道場で鍛錬をしていたらしい。一番めんどくせぇ奴が来た…俺はため息をつくと、の手を取り言った。
「終業時刻はとっくに過ぎた。教育係の阿散井にも許可を得た。コイツをどこに連れて行こうが問題無いだろう」
「今日は初日です。疲れているであろう彼女を思いやるのなら、もう休ませてあげてもらえませんか?」
そこには見えないはずの火花がぶつかる様子がなぜか見える気がして、も阿散井も、蓮の後ろにいた斑目も冷や汗が流れる。一方松本は腕を組み指を顎に当てていたかと思うと、この状況を打開しようと阿散井と一角に耳打ちする。そして嫌がる彼らの背中をドンと押した。
「…佐伯、お前はこっちだ。男同士飲みに行くぞ」
「何ですか突然。男同士の付き合いとか興味ないですし、と帰ります」
「バカかお前は。空気を読め、空気を!」
「…は?」
「とにかく、今日は飲み行くぞ!お前に拒否権はねぇ!」
「行かねーって…おい、行かねぇって言ってんだろ!引っ張んなっ!!」
「うるせー!オレらを助けると思って黙ってついて来いっ!!」
「意味わかんねーよ!離せーー!!」
嫌がる佐伯を引きずって、三人は道場を後にした。その姿をも俺も瞬きをして見送る。
「だ、大丈夫かな、蓮…」
「松本…お前、阿散井に何言ったんだよ…」
「まぁまぁ!うるさい奴もいなくなったし、こっちはこっちでご飯でも行きましょ!」
「ご飯?!行くっ!!」
着替えてくるから待っててー!と言いながら、目をキラキラさせて走り出す少女。俺はその白くて細い腕を咄嗟に引き、慌てて彼女を引き止めた。
「、走んな!!発作が…」
「やだな、冬獅郎!大丈夫だよ、私もう走れるの!」
「…そうだったな」
以前現世にいた頃、走ったことにより発作を起こす彼女の姿を何度か見ていた。それ以来止める癖がついてしまっていて、目の前にいる彼女が走ろうもんならつい止めてしまった。でもここは尸魂界。彼女を蝕む病は、もうない。俺は苦笑いを浮かべると、そっと手を離した。
........
.....
...
「美味しいー!このお魚、最高っ!このお漬物も美味しいー!」
ほっぺたが落ちそうな気がしたから、咄嗟に押さえながら頬張る。こんなに美味しいご飯を食べるなんて、生きていた時以来。温かで美味しい食べ物を口にできる幸せを改めて知り、私は箸を止めることなくひたすら食べていた。
「ほら、これも美味しいわよ!たぁんと食べなさい!」
「うん!ありがとう、乱菊さん!あ、これも美味しいー!」
「そんな慌てて食うな、俺のやるから」
「いいの?!ありがとう、冬獅郎!美味しいものを食べられるって幸せだね」
美味しくて楽しくて幸せで、何気なく言った言葉に冬獅郎も乱菊さんも固まった気がした。そんな二人に私は口いっぱいに頬張りながら首を傾げると、冬獅郎は少し切ないような、でも優しい笑みを浮かべる。そしてそっと箸を置いた。
「…」
「ん?なぁに?」
「そろそろ話してくれないか?なんでお前が東流魂街63地区にいたのか…記憶もどこまで残っているのか…」
「…そっか、話してなかったね」
東流魂街63地区…そこは治安は決して良くない場所だった。悪夢のような半年を過ごした場所。私は口に入っているものをゆっくり咀嚼し飲み込むと、箸を置いた。
「今から半年前、冬獅郎に魂葬してもらった後のこと―…」