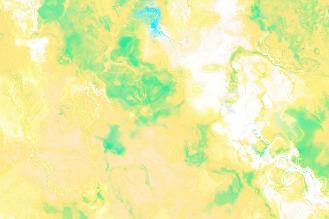
『戦闘集団』と聞いて、怖い人たちなのかと思った。
出会った瞬間、ボッコボコにやられちゃうんだと思ってた。
でも実際は全然違う人たちでー…正直戸惑いました。
Time to Shine 5
「蓮のバカッ!何で連れ出しちゃうの!まだ冬獅郎と話したかったのに!」
「うるせー!折角死神になれたんだ、起きたんならさっさと隊舎に行くのが礼儀だろ!」
救護詰所から担ぎ出されて向かった十一番隊の隊舎前で、私と蓮は言い争っていた。私はやっと再会できた冬獅郎といろんなこと話したかったのに、蓮が有無を言わさず私を担ぎ出してしまったのだ。昨日のことも未だによく理解できていないのに、私が救護詰所にいる間に死神になる許可が下りたらしく、二人まとめて戦闘集団と呼ばれる十一番隊の所属になったらしい。『戦闘集団』…私はここでやっていけるのだろうかー…。
「あ、レンレン、おはよー!」
「おはよっす、草鹿副隊長。今日からよろしくっす」
レンレンというのが誰のことか分からずにいるとすぐさま隣に立つ蓮が軽く頭を下げたので、私も続けて頭を下げる。レンレンって蓮のことか。パンダか、というツッコミは殴られても嫌なので心に秘めておこう。
それより蓮の発した『草鹿副隊長』ー…この小さい子が副隊長?昨日の隊長の集まりみたいなところにこの子もいた気がするが、あまり覚えていない。副隊長っていうと冬獅郎の隊の乱菊さんみたいな感じってことだよね…?私が頭を下げながらチラリと盗み見ると、草鹿副隊長と呼ばれた少女がにっこり笑って言った。
「クロ!元気になったー?」
「く、くろ?」
「うん、黒崎の『クロ』!」
そう言って私に飛びついて来たので、咄嗟に抱きとめる。夏梨や遊子よりも小さなその体はとても軽く、簡単に受け止められた。私は『戦闘集団』という言葉と今の状況との差異に頭がついていかず、とりあえず目をパチパチさせる。この小さい子が副隊長ー…レンレン…クロ……??
「わりーな、うちの副隊長、勝手にあだ名つけんだよ」
「へー、こいつが噂の子っすか…こんなガキにやられるたぁ、十一番隊もなめられたもんだな」
「うーん、『クロ』というより『姫』の方が美しいね」
混乱している状態のまま副隊長を抱き抱えつつ立ち尽くしていると、背後の扉がガラッと勢いよく開く音がしたのと同時に、三つの男性の声が聞こえた。振り向くと綺麗なスキンヘッド、赤髪、そしておかっぱ風の男性が立っていた。三人が入ってきたと同時に、腕にいた副隊長がするりと降り、三人に近付く。
「あれ?つるりん、まっつんは?」
「池松なら昨夜から現世っすよ。ほら、昨日副隊長との『あっち向いてホイ』に負けたバツで」
「えー、タイミング悪すぎー!まっつんにクロお願いしたかったのにー!」
「副隊長が指示したんでしょ…忘れたんすか」
つるりんさんのツッコミも無視して「デコピンの刑にしてやる!」と言う副隊長を眺めつつ、私は聞き覚えのある名前に反応する。池松さんって死んだ直後とこっちに来る前の門で会った、あの池松さんかな…?確か十一番隊って言ってた気がする。
「まぁいーや!そしたられんちゃん、クロのことお願いね!」
「はっ?!なんで俺なんすか?!」
そう言って声を上げるのは、赤い髪に顔に刺青の入った男の人ー…れんちゃんさんって言うのか。
「だってれんちゃんにレンレン任せたら、名前ややこしいじゃん!」
「「そこかよ!」」
れんちゃんさんとスキンヘッドさんがすかさずツッコミを入れる。何が何だかよく分からない展開に私も蓮も置いてきぼりな気がしているが、その鋭いツッコミがもう半年会えていない一護を連想させ、思わず微笑んだ。
「つるりんはレンレンよろしくね!」
「あぁ?!オレは人に教えるのとか向いてないっスよ?!」
「あ、ゆみちーはクロの髪整えてあげて!」
「言われなくとも!」
「おい、聞けチビ!」
つるりんさんと副隊長が騒がしく口喧嘩している横で「美しい姿に戻ろうね」と優しく微笑んでくれたのは、ゆみちーさんと呼ばれたおかっぱの男性。私にはもう何が何だか理解の範囲を超えていたので、流れに身を任せることにした。完全に思考放棄だ。勧められるがままに庭の真ん中に座らせされ、美容院よろしくカッパみたいなものを被せられる。
その様子を満足そうに見ていた副隊長は隊舎から出て行くようで、つるりんさんの頭を叩くと楽しそうに扉へ向かって行った。そして何かを思い出したのか一言「あ!」と言うと、振り返って笑顔で言った。
「言い忘れてたけど、剣ちゃんが『一ヶ月で俺が楽しめるくらいにまで強くさせとけ』って言ってたから、二人ともビシバシよろしくね!」
「「何バカなこと言ってんすか、あの人はー!!」」
「つるりんさん、よろしくっす!」
「つるりんじゃねー!斑目一角だ!」
「ちゃん、髪、肩口で揃えていいかな?美しいのに勿体ないねぇ」
蓮はいち早く順応したらしいが、私はカオスと化したこの状況を一向に飲み込めないまま、小首を傾げた。
........
.....
...
「たいちょー!何なんですか、アイツ!」
ドンっという机を叩く音と共に、松本の声が響き渡る。あの後、俺と松本は始業前に十番隊に戻り、お互い何も言葉を発さず黙々と仕事を始めていた。だが松本の我慢も限界に達したのか突然大声を出し、俺もシロも跳ね上がる。
「突然なんだよ、驚くだろ!」
「いいんですか、あんなこと言われて!」
「?」
「『こいつはオレの』とか、完全に隊長への宣戦布告じゃないですか!加えてあの、隊長以上の俺様的な態度!ムカつくー!!」
「あ゛ぁ?」
自然に俺への悪口も折り混ぜつつ、松本はシロのおもちゃを激しく振り回す。シロは松本が遊びたくて振り回しているわけではないのを感じ取っているのか、目の前で光速に動くおもちゃを追わず、どこか冷めた目で見ていた。は俺のではない…が、あぁ言われて腹が立つ気持ちがあるのは確かだ。一方で63地区というあまり良くない環境で、ここまでを守って来たのは間違いなくアイツだろう。そういう面では感謝している。
「アイツはこの半年、死に物狂いでを守ってたんだろうな」
「そうかもしれませんけど!でも、現世で多くの魂魄から守ってたのは隊長です!隊長の方がお似合いです!」
「…なんだよ、それ」
「とにかく!なんで隊長はそんな落ち着いてるんですか!取られてまさかこのまま泣き寝入りなんてしないですよね?!」
再びドンっと両手を机をつき、詰め寄ってくる松本。片肘をついて話していたものの、その迫力ある姿に数回瞬きをし、思わず吹き出した。その様子に松本はさらに逆上したようだが、そこまで松本に思われているとは考えていなかった。俺もも随分こいつに好かれているようだ。確かにあいつにああも言われて面白くないのも、「はお前のものじゃねぇ!」という気持ちをぶつけたいのも事実。
「…松本」
「なんですか、ヘタレ隊長」
「を取り戻すぞ、力を貸せ」
「そうこなくっちゃ!!ヘタレ撤回しますね!」
今すぐには無理だろうが、必ずを十番隊に入れる。その為にはまずアイツ…佐伯をどうにかしねぇと、という意見で一致した。どうすればアイツの邪魔なく呼べるのか…あるいはアイツごと異動させるにはどうしたらいいのか…。
「シロちゃん!!!!」
「「?!」」
松本と二人、仕事を前に一切手が動いていない状態で考えていると突然扉が開き、深く考え込んでいた俺たちはその音に飛び跳ねた。扉の先に立つ雛森は小さな荷物と斬魄刀を所持している。どうやら任務前に立ち寄ったようだ。
「ひ、雛森…びっくりするじゃない…」
「びっくりじゃないですよ、乱菊さん!シロちゃん!あのって子、シロちゃんの何?!」
今まで見たこともない剣幕で机まで来ると、バンッと机を叩かれた。今日はよく机が叩かれる日だ。普段の落ち着いた様子との対比に俺はさらに驚きつつ、彼女の発した言葉の意味を考える。そういえばー…
「お前、と知り合いだったな」
「知り合いじゃないよ!知らないから聞いてるの!」
「…?でも昨日、アイツの名前に反応したよな?」
「名前くらい覚えてるよ!って、去年シロちゃんの誕生日に現世に呼び出した子でしょ?」
「…なんで現世って…」
「去年から頻繁にシロちゃんが現世に行ってたの知ってる。それってあの子に会ってたんでしょ?春のテーマパークだってそう!」
「…」
「それにあの子、昨日間違いなくシロちゃんの名前呼んでた!何で現世にいた子が『記憶のある状態で』ここにいるの?!」
「「?!」」
一気にまくし立てる言葉に、俺も松本も目を見開く。確かに昨日のあの反応で、雛森がのことを知っている(正確には名前を知っている程度だったが…)のは把握していたが、まさかが現世にいた人物で、さらに記憶を残したまま来たことまで辿り着いているとは思わなかった。流石だな、と感心した。
目の前には片手を机についた状態のまま腰に手を当て、何故か腹立たしそうなオーラを纏う幼馴染…その状況に俺は無言で脳内を整理し始めた。いずれにせよ雛森がの味方になってくれたら、も姉のような存在が出来て安心するのではないか…。
「ねぇシロちゃん、黙ってないでなんとか言ってよ」
「…とりあえず…お前なんでそんなイラついてんだ?」
この一言を言った次の瞬間にはいつかの記憶と同じようにクッションが飛んできて、俺は綺麗にかわす。
「あっぶねーだろーが!!」
「シロちゃんのバカ!!!」
「あぁ?!何だ、突然!」
「もういい、帰ってきたら全部説明してもらうからね!もちろん奢りで!!」
彼女は言うだけ言うと、来た時同様激しく戸が閉め、出て行った。嵐が去ったかのように、再び執務室には静けさが戻る。
「…なんだ、アイツ…?」
「隊長、いくらなんでも鈍すぎです…」
頭を押さえため息をつく松本の声に、俺は眉間の皺を深くした。