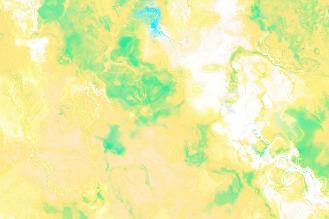
きっと今頃、新しい家族と楽しく暮らしているはずだ
現世では出来なかった分、たくさん走り回って遊んでいるだろう
毎日、あの花のような笑顔を振りまいているに違いない
…そう思って平和に過ごしてきたこの半年を、俺は後悔することになる。
Time to Shine 2
頭をよぎる嫌な予感を振り払い、何とか一番隊へ着く。途中十一番隊へ寄り池松を責め立て台帳も確認したが、やはりは潤林安へ割り振られていた。となると、やはり偶然にも同じ髪色、瞳の色の少女の起こした事件なのだろう。そう思い込もうとしても、胸騒ぎは抑えられなかった。
部屋へ入り、俺は無言で定位置に着く。その後ろに副官の松本が控えた。いつもとは違うその雰囲気に、他隊の隊長格も少し不安気な雰囲気が漂っていた。
しばらくすると扉を開く音が響き渡り、一斉にそちらに目線をやる。まず総隊長の山本が入り、その後ろから入って来たのは、両腕を隊員に捕らえられながらも何度も逃げ出そうとする、傷だらけの男。身長は高く、生きていれば見た目は10代後半くらいだろう。そして後ろには少年同様隊員に引かれ、両腕を縛られ、身体中泥で汚れ着物は所々裂けている、俯くオレンジ色の髪の少女が続いた。目の前を通過する少女から放たれている霊圧は感じ慣れたそれで、思わず握った拳に力が入る。そしてずっと記憶にあった半年前の花のような笑顔との対比に、俺も松本も言葉を失った。
見覚えのある白いカバンは泥に汚れ、そこにいたはずの赤鼻の人形の姿は見えない。長く真っ直ぐで綺麗だったオレンジ色の髪はバラバラの長さに切られており、その身体は小さく震えているのがわかった。この半年間、彼女がどう生きてきたのかが一目で見て取れて、後ろの松本が苦しそうに俺を呼んだ。
「隊長…」
「…」
「…あの子、潤林安にいたんじゃないんですか…?なんで…」
「…」
一体何があったのか…何故63地区なんて場所にいたのか…直ぐにでも探してやればよかった。後悔の念が押し寄せる。ふと彼女の手元を見ると、その手に強く握られているのは以前渡した千歳緑。切れたのか今はただの短い紐のようになっている。切れたことにより俺の施した霊力の制御が出来なくなっており、本来の霊力が溢れ出している。その霊力の高さと彼女自身の柔らかで暖かな霊圧に、何人か驚きの声を上げていた。
部屋の中央に連れ出されたは小さく震え、俯いたまま動かない。そんな彼女に山本は少し霊圧を上げて問い詰め始めた。
「女、名はなんという」
「…」
「何故に霊力を解放し、人々を傷付けた?」
「何も話すな!こいつらなんか信用すんな!」
「黙れ!!」
その瞬間、少年は取り押さえられていた隊員に殴られた。はその音に反応すると、目を見開いて駆け寄ろうとする。だが力の弱い彼女はあっという間に引き戻され、俯いてしまった。きつく結ばれた手に、さらに力が込められたのがわかる。
が駆け寄ろうとしたあの少年は、一体何者なのだろうか。この少年も、彼女ほどではないが高めの霊力を感じる。こっちに来てから一緒に行動してたやつか…? 山本はじっとを見下ろしていると、は何か決心をしたのかぱっと顔を上げ、山本を見る。その表情は今まで見たこともないような【怯え】が見え、今すぐにでも駆け寄りたい衝動に駆られた。
「…あの…一つ確認しても、いいですか…?」
の小さな声が響く。山本は指を組んだままじっとを見ていて、返事はしない。それを是と捉えたはちらりと横に捉えられている少年を見て、小さく頷いた。
「ここにいる皆さんは…本物ですか?」
「どういう意味じゃ」
「…あそこでは、よく【死神】を名乗る人間の姿をした虚が現れ私たちを騙し、殺そうとして来ました」
「?!」
「今回もそうでした。私に襲いかかって来た男の人は最初は普通だったのに、突然目が真っ黒になって人間じゃなくなった。私も蓮…彼も必死に逃げようとしていたんです」
そしたらあんなことにー…そう小さく発した声は、今にも消えてしまいそうだった。は握りしめている手にさらに力を込め、山本を真っ直ぐ見つめて言った。
「信じた人に殺されるような思いは、もうしたくありません。あなた方は【本物の死神】だと、信じていいですか…?」
山本はその問いに答えず、ただじっとを見下ろす。その目は何か考えているように見えた。その時、何処からか一羽の蝶が舞い込んできて、山本の指先に止まる。何か伝令があったようで、役目を終えると静かに飛び去っていった。
「確かに今回、お主の殺めたヤツは人の形をした虚のようじゃ」
「…」
「だが、我が護廷十三隊の者を不容易に傷つけたのも事実」
「!!そ、それは…」
「こやつらの処遇を…」
「悪いが、一言いいか?」
怯えた様子のを前に黙っていられなくなった俺は、山本の声を遮る。その声に反応したのか、は勢いよくこちらへ顔を向けた。顔は泥と傷がついているが、驚いている表情なのは見て取れる。そして俺と、俺の後ろに立つ松本を交互に何度も目をやると、次第にその大きな瞳に涙が浮かび出す。そして俺の目をジッと見ながら、小さく口を動かした…それは間違いなく、俺の名だ。
その瞬間、後ろに立つ松本が声を震わせ小さく俺を呼ぶ。あぁ、わかってる。理由はまだ分からないが、あいつのあの反応は俺たちのことを覚えている。そう確信すると、無意識のうちに口角が上がった。
「女の方は俺の知り合いだ。よって十番隊で預からせてもらいたい」
「シロちゃん?!」
雛森の驚く声が響き渡り、辺りは騒然となる。やっと見つけたんだ、ここで処遇だなんだ言ってられるか。誰がなんと言おうと、は俺が引き取る。山本は俺をじっと見つめると、ふむ…と興味深そうな表情を浮かべながら見下ろして来た。
「知り合い…日番谷、東流魂街のあんな外れに、なぜ知り合いが?」
「それはー…」
「私の出身地がその辺りでして、その繋がりです」
咄嗟に理由が思い浮かばない俺をカバーするように、松本が先ほどとは真逆のはっきりとした声で発言する。その声はこの繋がりを否定させないような、そんな強い意志を感じた。もし本当のことー…つまり現世の頃の知り合いと言っても、結局は「いつ?」「何故?」が始まるだろう。そしてそもそもの記憶が残っていると知られたら、それこそ十二番隊行きになる可能性が高い。それは避けたい。確かに松本は東流魂街出身であり、確か62地区。が発見されたのはその一つ先の63地区ー…となると…
「はぁ?俺知らへんし。しかも63地区とか62地区通り過ぎるやん」
「ギンは黙って!」
俺の予想通り、市丸が口を出してきた。いつもは招集の場では立場をわきまえる松本も、やっと見つけたのことで必死でつい素の反応をしてしまったらしい。慌てて口を塞ぐと、睨みながら「失礼しました、市丸隊長」と言い直した。そんな松本の様子を市丸は大して気にもせず、自らの後ろに控える吉良と何か話し始める。山本はふむ…と考えると、髭を撫でながら再び口を開いた。
「では日番谷、仮に十番隊で預かるとして、その後はどうするつもりじゃ?」
「見ての通りの霊力だ。俺が責任持ってコイツを死神にする」
「……」
死神になりたいと言っていた。想像していた再会の形とは違うが、俺が育ててやるのも悪くない。すると山本は「流石日番谷じゃな…」と漏らし、言葉を続けた。
「お主らも感じておろう、此奴らの霊力の高さを。今は死神不足でもある。よって処遇として、護廷十三隊に入れようかと考えておった」
「「?!」」
時間も惜しいのでその場で受け入れる隊を決めてもらおうと、今回特例で副官にも参加義務を伝達した、といった。予想外の言葉に再度辺りは騒つく。隊員を傷付けたことは事実だが、逆を返せば戦闘集団の十一番隊を一気に捩じ伏せたのだ。確かに味方につけるのが一番有効だろう。それぞれの隊が副官と相談しているようだが、しばらくするとその騒めきから一つ声が響いた。
「せやったら、三番隊で引き取らせてもらえへん?」
「「?!」」
「二人まとめてはあかんのなら、嬢ちゃんだけでもええで」
『そらもう責任持って、一から十まで親身になってあれこれ教えるで!』と言葉を続け、一斉にその発言元…市丸に視線が集まった。発言した当の本人は飄々としていて、何を考えているのか全く読めない。俺は怒りのあまり握っていた拳を震わせた。
「却下だ、却下!お前はアイツと関係ねぇだろ!」
「関係なんか誰しも初めはないもんやで。そんなん徐々に築くもんやろ」
「ちょっとー!あの子たちはうちが見つけたんだから、二人まとめてうちに入るんだよ!ね、剣ちゃん!」
最初の緊迫した空気から一転、十三隊に入れるとなった途端各隊の引き抜きが始まった。男の方はどこへ行っても構わないが、だけは何としてもうちに入れる。
「草鹿!お前んとこなんか入れたら、あいつの体がもたねぇだろ!」
「あいつ?!ちょっとシロちゃん、あの子誰なの?!なんで知り合いなの?!」
「七緒ちゃーん、あの子綺麗にすれば絶対可愛いよねぇ?欲しいよねぇ?」
「だぁぁー!!うるせー!!」
その空気をは中央で一身に受けながら、涙も何処へやらキョトンとした顔で一人一人を見やる。一方の少年も先程までの威勢はどこへやら、相変わらず両腕を隊員に捕らえられたままポカンと口を開けて見回している。
「とにかく!あいつは十番隊にー…」
「いいえ、まずは四番隊に来ていただきます」
そう静かに声をあげたのは、卯ノ花。その声には静かながらも有無を言わさない、強い主張を感じた。
「皆さん、彼らが怪我をしているのに自隊のことばかり。一体何を考えているのですか。十三隊に所属するならば、まずは治療が先決です。勇音」
「はい!」
そう言うと虎徹は中央にいるの元へ移動し、肩を抱いて扉へと向かう。そんな中でもは振り返ると不安そうな瞳で少年を見やり、その後こちらを見てきた。俺は安心させようと小さく頷いた。
のいた場所には彼女自身の温かで懐かしい霊圧と、彼女には似合わない血生臭いが匂いが残っていた。