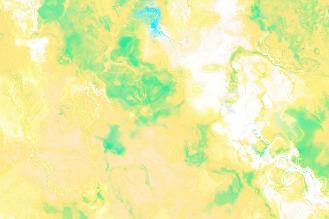
真っ直ぐなオレンジ色の髪
透き通る白い肌
光が集められている綺麗な瞳
花のような可憐な笑顔
今まで彼女の容姿を聞かれたら、俺はきっとこう答えていただろう。
だが久し振りに会えた少女はそれと大きくかけ離れていて、早く捜し出さなかった自分を何度も責めることしか出来なかった。
Time to Shine 3
バタンッという音と共に、重い扉が閉まる。俺も松本も彼女が去った後も扉を見つめていた。その後を追うように隊員に両腕を取られたまま、少年もその場を離れようと山本に背を向け歩き始める。
「おい、じぃさん」
静寂を破ったのは、未だに腕を捕らえられている少年。首だけをこちらに向けじっと山本を見ている。その表情はどこか嬉しそうで、八重歯が小さく見えた。
「よくわかんねぇけど、お前らは本物の護廷十三隊で、俺らを死神にしたがってるってことか?」
「お前、言葉に気をつけろ!」
腕を抑えていた隊員に思いっきり殴られる。口が切れたようで、男は血の混じる唾を吐くと、殴った隊員を睨みつける。その目は今まで生きてきた過酷さを物語るかのような鋭さで、隊員は小さく息を飲んだ。その様子を見ていた山本は『ほぅ…』と言うと、睨みつけている男に声を掛けた。
「男、名は何と申す」
「…佐伯 蓮(レン)」
「佐伯、お主の腰元にあるのは斬魄刀か?」
「ざんぱくとう?」
佐伯と名乗る、見た目は人間でいう10代後半くらいの少年は、確かに腰に刀を差している。その本数は、二本。佐伯はあぁ、と言うと両腕を抑える隊員を振り払い、刀を外す。
「斬魄刀ってのかよくわかんねぇけど、こっちは俺の刀で、こっちは俺のじゃねぇ」
「…というと?」
「これは…お前らの仲間がさっき連れて行った女の刀だ」
「?!」
の名に反応したのは、俺でも松本でもなく雛森だった。その声に驚き雛森を見ると、雛森は俺をキッと睨んでくる。何なんだ、一体。やはりと何かあったのだろうか…。俺が小さく首をかしげると、後ろから松本のため息が聞こえた気がした。
それにしてもも斬魄刀を持っているとは…まだ分からないが、もしかしたら想定以上に力を身につけているのかもしれない。それはそれで見るのは楽しみではあるが、この半年で【斬魄刀が必要になるくらいの何か】が、彼女の身に起きていたということになる。彼女のこの半年間を考えると胸が痛み、キュッと合わせを握った。
佐伯との引き抜きにどの隊も躍起になっている中、後ろに控えていた松本がそっと声を掛けてきた。
「隊長、私の様子見てきます」
「あぁ、頼んだ」
「隊長は絶っっっ対に、を他の隊なんかに取られないで下さいよ!」
「…当たり前だ!」
.....
....
..
ふと目を覚ますと視界には真っ白な天井が見え、視界の隅に点滴の袋を捉えた。その光景は余りにも身近だったものと重なり、一瞬現世にいるのではと錯覚を覚える。だがすぐに違うことを思い出し、勢いよく体を起こした。体を起こしたことにより短くなった毛先が視界で揺れ動き、この半年の悍ましい日々が蘇る。私は体を小さく丸め、顔を布団に埋めた。
「あ、目が覚めましたか?」
優しい声が耳に入り、ふと顔を上げる。そこにはタレ目の見るからに人の良さそうな少年が、新しい点滴を持って立っていた。少年は私のベッド脇に近付くと点滴をスムーズに交換していく。
「あの…ここは?」
「四番隊の救護詰所です。ここに来られるや否や、気を失われたんですよ」
あの出血量でむしろよくここまで歩けましたね、と小さく微笑んで言う少年は、とても柔らかい雰囲気を醸していた。こっちに来てから、蓮以外で初めて『人の雰囲気』を感じた。
ふと自分の手元を見れば、数え切れないほどあった切り傷や擦り傷、泥の塊は綺麗にされている。布団をまくれば清潔な真っ白な着物に替えられていて、裾をまくれば足にあったはずの血と泥の塊の姿もない。ずっと砂にまみれてしまっていたあの翡翠も、今は綺麗に見える。そして血を流し過ぎて貧血気味だったのに、その気配もない。間違いなく、この目の前の彼が治療してくれたのだろう。
「治療していただき、ありがとうございました…えっと…」
「あ、僕は山田花太郎といいます。あなたは?」
「黒崎です」
「さん、よろしくお願いします」
二人揃って頭を下げる。久し振りのほっこりした空気に、なんだか心が暖かくなる。彼は本物の死神だと信じたい…。私は先程見るからに地位の高そうなお爺さんにした質問を、目の前の彼にも同じようにした。
「花太郎さんは、本物の死神ですか?」
「えっと…仰ってる意味がよく分からないですが、僕は死神で、僕自身は偽物ではないので、本物の死神だと思います…多分…」
これって答えになってますか?と不安そうに言う花太郎さん。そう言われても私自身もよく分からず、二人で首を傾げる。ただ、今まで見てきた【人間の形をした虚】は頻繁に私のことをまるで獲物を狙う鷹のような目で見てきていたため、彼のこの目は虚ではないと思えた。
「じゃあ、あそこにいた冬獅郎も?」
「冬獅郎…あ、日番谷隊長ですか?この瀞霊廷内で偽物の日番谷隊長をお見かけしたことがないので、恐らく本物かと思いますよ」
「そっか…そうなんだ…」
今まで遭遇した虚は、恐らく私の心を映すものだったのだろう。ここに来るまでに、冬獅郎の姿をした虚に何度も騙され、何度も殺されかけた。身も心も傷ついて、冬獅郎の姿をしたヤツになら殺されてもいいかなって思う時すらあった。でも、それももう終わり。やっと本物に会えた。そう思うと溢れるものが止まらず、私は俯く。花太郎さんは私が泣いていることに気付いて気を利かせてくれたのか、静かに離れて行く気配を感じた。そして扉を閉めるとき、そっと声を掛けてくれた。
「この部屋は結界を張って面会謝絶にしろと、卯ノ花隊長より言われております。四番隊の隊員以外は【さんが内側から開けるまでは】誰も入って来られないので、安心して休んでくださいね」
明日の朝また来ますね、と言うと部屋の明かりを消し、花太郎さんが部屋を出ていった。卯ノ花隊長がどなたなのか存じ上げないけれど、二人の気遣いに心が温かくなり余計に涙が溢れた。
********
しばらく流れるがままに涙を流していたけど、少し落ち着きを取り戻し顔を上げる。今私がいるのは清潔感のある真っ白な部屋。窓にカーテンが引かれているが、ぼんやりと明るい光が部屋を照らしている。月明かりのような気がするので、恐らく夜なのだろう。ふとベッド脇のサイドテーブルを見れば、あの時千切れてしまった千歳緑のお守りが置いてあった。こっちの世界に来てからずっと心の支えにしていた、大切なお守り。よかった、捨てられていない。
チリン…
扉の方から突如鈴の音がして、勢いよく視線を向ける。よく見ればうっすらと扉が開かれていた。誰も入って来られないんじゃないんだっけ…怖い…また命が狙われているのだろうか。こっちに来てからずっと一緒だった蓮は今いないし、相棒の刀もない。蓮はどこにいるんだろう。そう思い怯えながらじっと見つめ、入って来るであろう人物をじっと見やる。だが、扉は人が通れないほどの大きさにしか開かれず、一向に人影は見えてこない。そしてそのまま、何事もなかったかのようにゆっくり閉じていった。
すると足元から『ミャー』という鳴き声が小さく聞こえた。ふと見ると、そこには見覚えのある翡翠色の瞳に真っ白な毛並みのもこもこが一匹、小首を傾げこちらを見上げている。
「…シロ?」
名を呼ばれたことで嬉しそうにミャーと鳴く真っ白な仔猫は、まるで抱き上げろと訴えるかのようにベッドをカリカリかく。このふわふわはシロだ、シロに間違いない。私はそっと手を伸ばし抱き上げると、ふわっとシャンプーのいい香りがした。シロがいるってことは、やっぱりここは本物の冬獅郎のいる世界だ。でも何故シロは結界を破って入って来れたのだろうか?対人間の結界なのか、四番隊の誰かが入れてくれたのか…。
シロは大人しく私に抱きしめられていたが、しばらくするとしきりに自身の首元を気にしだした。まるで何かを伝えたいかのように、何度も首元を掻き、擦り付ける。そこにあるのは私のお守りと同じ色で、鈴のついた可愛らしい首輪…に結び付けられた、小さな紙切れ。私はシロの首元にあるその結び目をそっと解いた。
《窓開けて!》
文末にはセクシーなキスマーク…乱菊さんだ!キョロキョロと辺りを見回して誰もいないことを確認する。そしてベッド脇にある窓のカーテンを勢いよく開けると、そこには大きな月が辺りを照らしていた。私は指示通り、窓を開ける。するとそこから少し秋の匂いの混ざり始めた新鮮な空気が入ってきたのと同時に、私の視界は一瞬にして白と黒の世界に包まれた。その暖かな温もりとこの香りは手紙の送り主の乱菊さんではなく、こっちの世界に来てからずっと探していた人のものー…。
「とう…しろ?」
「…」
小さく私の名前を呼び、頭を抱き寄せられさらにギュッときつく抱き締められる。その力強さと安心感に、私の視界は一気に滲む。
「…冬獅郎っ!!」
私は点滴をしていることも忘れ、彼に腕を回し、力一杯抱きしめる。そして感情のままに何度も彼の名を呼び、涙を零した。そんな私に彼は何度も私の名を呼び、きつく抱き締め返し続けてくれた。