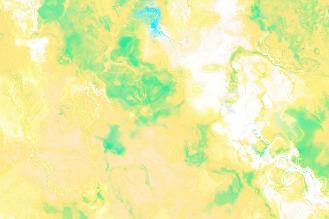
今日は十一番隊の焼き芋大会。
祭り事が大好きな自隊の人たちは、正直祭りの対象が芋であろうと栗であろうと、お酒が飲めて騒げて何なら筋肉自慢ができる集まりなら、何でもいいのだろう。そんな日常を楽しんでいる自分も、随分ここに慣れたものだ。
澄んでいる冬空を見上げれば、現世の頃と同じ綺麗な青空が広がっていた。
邂逅
「ー、早く芋持ってこい!」
「はーい、今持っていきまーす!」
池松さんに言われ、ホイルに包んだ山のようなサツマイモを持っていく。火の周りにはじゃんけんにより番を任された、彼と私しかいない。季節ももう冬と呼べるだろう。寒空にパチパチと心地よい音が響き、私は目の前でユラユラと揺れる炎をぼーっと見つめる。その光景にふと、遠い記憶が蘇った。
「懐かしいなぁ…」
「ん?」
「子供の頃さ、家の庭でよく焼き芋やってたなぁ…って」
ポツリ零すと、池松さんは一言「ふーん」と言った。懐かしさから零れた言葉で、これに対して特に返事は期待していないし、話が広がるとも思っていない。けれど意外にも、彼は話を拾ってくれた。
「どーせ火傷する口だろ、お前」
「大正解!焼き芋で手のひらいっぱいに火傷したことがあってさ、流石に大泣きしたよ!」
「…そうだったな」
そんな池松さんの反応に、私は首をかしげる。はたして彼に今まで、この話したことあっただろうか。いや、ない。これはまだ私が4つか5つだった頃の話で、今の今まで私だって忘れていたほど、記憶の遥か彼方に追いやっていたものなのだから。池松さんとはやっぱり何か繋がりがある気がする…そんなことを考えていると、彼は私の頭を小突いて言った。
「った、何する…」
「あんま怪我すんなよ、一応女の子なんだから」
「え…」
あれ、その言葉何処かで…。小突かれた頭を抑え抗議しようとしたが、彼の言葉によってその口は止まった。止まらざるを得なかった。急に固まった私に驚いた池松さんは、訝しげな表情を浮かべて言う。
「な、なんだよ」
「…いや、昔焼き芋で火傷した時、同じように言われた気がして…」
「…お前の兄貴か父親じゃねーの?」
「んーん、二人はぶっきらぼうだから、そんな優しい言葉では言わないよ」
二人な優しさとはまた違う感じの、見た目も話し方も優しい男の人のような気がするんだけど、あれは一体誰だっけ…。全然思い出せない。あれは確か火傷して大泣きした後に一人火から離れて座っていた時、包帯でぐるぐる巻きになった私の手を取って、優しいお兄さんが言ったんだ。
ー…あんまり怪我するなよ、。一応女の子なんだから…。
…って。あれは誰だっただろうか…なぜ忘れてるのだろうか…思い出したくても思い出せない。無意識のうちに眉間に皺を寄る。そんな私の顔を見るなり池松さんはニヤリと笑うと、勢いよく私の鎖骨あたりに手を這わせてきて、私の眉間に鎮座していたはずの皺はどこへやら、思わず肩が上がる。
「ちょ、何するの!」
「なーにさっきから難しい顔してんだよ!ほら、笑え!」
「ちょ、やめ、くすぐった…はははっ、やめてってば!」
元々くすぐりには弱い私だが、特に首元がダメだ。首元に手を置かれるだけでも身体中がぞわぞわして、くすぐったくて仕方ない。一通り笑い終えると、池松さんは微笑みながら離れていった。それにしても、何故彼は私がくすぐったいと感じる場所を知っていたのだろうか。首元以外にも人がくすぐったく感じる場所なんていくつもあるのに、何故池松さんは「笑え」と言って、ピンポイントで私が一番苦手な場所を攻められたのだろうか。行き着くところはやはり…。
「ねぇ池松さん。やっぱり私たち、前に何処かで会ったことあるでしょ」
その確信めいた質問に、池松さんはちらりと横目で私を見る。そして小さく笑うと、空を見上げた。
「いーや。オレとお前が初めてちゃんと会ったのは、間違いなくお前が死んだ日だ」
「でも…」
「ただオレはお前のことを、お前がガキの頃から知ってる」
「なっ…」
そこまで言うと私の手よりもずっと大きな手で、私の頭にポンと手を置いた。そして顔を覗き込むようにして言葉を続けた。
「首元が弱いのも苺が好きなのも、なんなら幼稚園の運動会でコケたことも知ってる。更に言えば、お前同様霊力の高いお前の兄貴や父親のことも…あー、でも妹どもの話はあんま聞いてねーな」
「何で?どう言うこと?聞くって誰から?空座町の担当は池松さん本人だったよね?」
言っていないはずの情報がポンポン出てきて、頭は軽くパニック状態だ。確かに池松さんは私が死んだ時、空座町担当だった。でも担当なんてコロコロ変わる…ってことは前任者から聞いたとか?だとしても町には何万人も住んでいる。何万分の一で私たち家族のことを詳しく知る意図がわからない。私が混乱した表情をしていたのが分かったのか、池松さんは私の頭に置いたままだった手で、そのままくしゃりと柔く撫でた。
「悪い、まだ言えねー。ただ、敢えて言うなら…」
「…?」
「『守ってくれてありがとう』」
「っ?!どういう意…」
「奏ー、そろそろ焼けたかぁー?」
「おー、いい頃合いだと思うー」
私たちの会話を遮るように、恋次くんがいくつかのお皿を持ってこちらにやって来た。思わず口を噤んだ私を無視しながら、まるでこれが自然だというようにホイルに包まれた芋を1つ掻き出すと「何処がだよ、少し焦げてんじゃねーか!」と池松さんをどつく。そして二人はそのまま楽しげに芋談義を始め、私は先ほどの話の続きを聞きたくても聞けない状況になってしまった。その間にも池松さんは焼きたての芋をほいほいと掻き出し、熱そうに皿に乗せていく。
「ほら、日番谷隊長に持っていくんだろ。これ持ってけ」
「え、でも…」
「いーから!行った行った!」
そう言って渡された焼き芋は既にカゴに入っていて、私が火傷しないようになっている。私はまだ先ほどの話の続きを聞きたかったけどそれ以上は聞けなくて、小さく頷くとカゴを手に冬獅郎の霊圧を探った。
********
先程の池松さんの話を気にしつつ、冬獅郎の霊圧を探る。するとそれはいつもいる十番隊の執務室ではなく、私が今まで敢えて避けていた場所にあった。執務室に置いておこうかとも思ったが、シロが匂いに反応してイタズラしかねない。それより何より、私が直接焼きたてを渡したい。そして一緒に『美味しいね』と食べたいー…出来るなら、焼きたてを。私は「よし!」と呟くと、気合いを入れてその場所を目指した。その場所とはー…
「失礼します。十一番隊第十五席、黒崎です。日番谷隊長はおられますでしょうか?」
「あぁ、どうぞ」
冬獅郎のものとは違う、大人の男声での返事にガラリと扉を開ける。中にはお茶を囲む藍染隊長と雛森副隊長、そして冬獅郎がいた。
「いらっしゃい、くん」
「こ、こんにちは、藍染隊長」
藍染隊長とはきちんと話をしたことがない。席官就任時のお披露目会で初めてお会いしたが、その視線が流魂街にいた頃の虚のものと似ている気がして、そこから勝手に苦手意識を持ってしまっている。
「どうしたの、ちゃん。こんな所に来るなんて珍しいね」
そう言って笑顔を向けてくれる雛森さん。悪意はないだろうが、彼女のことがどこか苦手な私にはその言葉が「何しに来たの?」に聞こえて、池松さんから手渡されたカゴにキュッと力が入る。
「突然すみません、冬し…日番谷隊長に焼きい…お届け物をする約束をしておりまして…」
「あぁ、もう焼けたのか。悪い、長居しすぎた」
高級そうなお茶菓子を前に何となく『焼き芋』と言いづらく、届け物と言って言葉を濁した。そんな私を冬獅郎は気にすることもなく立ち上がると、私の方へと足を踏み出す。するとその足を止めるかのように、彼の横に腰掛けていた雛森さんは「シロちゃんのお茶入れ替えたばっかりだし、もう少しいなよ」と彼の手を握った。そんな彼女の華奢な手の白さが、何故かとても目につき、視線を外す。
「いや、迎えも来たしそろそろ失礼する」
「えー、シロちゃんの大好きなとっておき、まだ出してないのに!」
「とっておき…?」
「そう、ちゃん知ってる?」
「…いえ」
そういうと雛森さんはニコリと微笑み、「じゃーん!」と言いながら棚から『甘納豆』と書かれた袋を取り出す。冬獅郎は甘いものが好きじゃないと思っていたが、甘納豆は別なのか…知らなかった。「子供の頃、よく一緒に食べたよねー」と楽しそうに話す雛森さんは私と目が合うと、ニッコリ微笑んだ。その微笑みが何となく嫌でふと再び視線を外せば、目に入るのはお洒落なお茶菓子と高級そうな日本茶、そして彼女が彼の為に準備した、彼の好物。一方私の煤で汚れた手元にあるのは、少しばかり焦げた焼き芋。その差が「隊長副隊長」と「ただの席官」に見えて、心がざわつく。
…出直そう。
先ほどまでは早く会って一緒に食べたいと思っていたのに、今度は今すぐこの場を離れたくなった。何故かは何となくわかったけど、今は考えない。
「すみません、みんなを待たせているので失礼します」
「あ、おい!」
私は頭を勢いよく下げると手渡すことのなかったカゴを強く握り、そのまま五番隊を飛び出した。後ろで冬獅郎が私を呼ぶ声が響いていたが、振り向く余裕なんかない。一体何しに来たんだ、私はー…。
走って走って、十一番隊のみんなの元へ戻る。あと少しのところで、私に気付いたみんなが「何そんなに走ってんだよ、お前!」と笑っていて、その様子に気が抜けて足がもつれる。あっ…と思った瞬間私は豪快にコケて、焼き芋がコロコロと散らばった。
「おーい、大丈夫かよー!」
「寝ぼけてんのかぁー?」
「なぁに芋ぶちまけてんだよ、黒崎ー!」
十一番隊のみんなは笑って、地面にうつ伏せで倒れている私に声をかける。早くあの輪の中に入ろう、立ち上がらなきゃと思うのに、視界が滲んで立てない。こみ上げるものが止められなくて、顔を上げられない。
私の知らない、二人の時間
綺麗なお茶菓子
芳しい香りの広がる日本茶
知らなかった好物の甘納豆
冬獅郎の手を掴む、真っ白で綺麗な手
どれを思い出しても、心が騒つく。幼馴染だと言う『二人の絆』と『立場の違い』を思い知らされらた気がする。私の異変にいち早く気付いたのは焼き芋を持たせてくれた池松さんで、他の人たちとは違って頭のすぐ上から声がする。近づき、しゃごみこんでいるようだ。
「どうした?芋、渡せなかったか?」
「…」
「ほら、立てるか?」
池松さんの優しい言葉に涙腺は崩壊してしまい、とてもじゃないが顔を上げられない。私が泣いたせいで、みんなの楽しい場が台無しになる。それはダメだ、絶対に。かといってこの涙はすぐには止まらなそうだ。いろいろとぐちゃぐちゃ考えて、私は俯せで倒れたままとりあえず顔を横に振る。すると「まったく…仕方ねぇな」と言うと、私の脇の下に手を入れられた。そしてそのまま、みんなからは見えない方向へ顔が向くように抱き上げ起こしてくれた。池松さんに比べたら全然小さな私の体は簡単に起こされて、見上げれば私の顔についた砂を拭ってくれる大きな手が伸びてくる。「あーあー、顔に傷できてんぞ」と笑って見てきていて、その笑顔にまた視界が滲む。
「…池まっ…」
「悪い。そいつ、借りられないか」
「?!」
突然背後から聞こえた声に、私は固まる。その声は間違いなく、数分前に私の心をギュッと締め付けた相手そのもので…。池松さんは私の様子を見下ろして小さくため息をつくと、ポンっと頭に手を置いた。
「いーっすけど…あんまコイツのこと虐めないで下さいね。オレにとっては妹みたいなヤツなんで」
「?!」
「あぁ、すまない」
妹…池松さん、そんな風に思ってくれていたんだ。その事実が心の底から嬉しい。呆然と見上げている私に「渡すんだろ?」と優しい笑みを浮かべつつ、いつの間にか再びカゴに戻っていた焼き芋を手渡される。その瞬間右手に泣かされた張本人の温もりを感じ、そのまま強く引かれ歩いた。
振り向くと池松さんはニコニコしながら、手を振ってくれていた。
********
「で?お前は何故オレが呼び止めたのに止まらなかった」
「…」
「焼きあがる頃に執務室にいなかったのは悪かった。ただ、泣くことねーだろ」
「…」
「そんなに早く焼き芋食いたかったのか?」
「ちがっ…!」
「じゃあ何だよ、言わなきゃわかんねーよ」
「…何でもない!冬獅郎のばーか!」
このモヤモヤの正体を、私はまだ見て見ぬ振りをするー…。