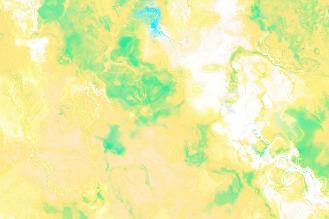
素直に喜んで、微笑みあうこと
素直に怒って、ぶつかりあうこと
素直に哀しんで、一緒に涙すること
素直に楽しんで、共に過ごせる時間に感謝すること
これらのことを【誰と一緒にしたいか】と考えた時、真っ先に思い浮かぶのは君でしたー…。
Time to Shine 12
終業後、恋次さんに連れられてやってきたのは『あっち向いてホイ罰ゲームからの帰還、お疲れさまっつん会』(命名:副隊長)という、長ったらしい名前の付いたの飲み会だった。私はまだ十一番隊に入る前だったので詳しくは知らないが、どうやら私が護廷に連れてこられたその日の朝、副隊長主催の『超真剣勝負あっち向いてホイ大会』が開催されていたらしく、そこで最下位となった池松さんはその日の夕方からこの三週間近く、強制的に現世に派遣されていたらしい。
「この三週間、どこ行ってたと思います?十一番隊担当地区の中で最も過酷な、あの北極近くの村っすよ?!寒いし暗いし虚はバカみてぇに現れるし、最悪でしたよ!」
「おーおー、自分の運の無さを後悔すんだな!」
「本当はあそこ、次は斑目さんたちが当番だったはずじゃないっすか!なんで俺がっ!」
「まっつん、仕方ないよー!だってまっつんあっち向いてホイ、上しか向かないんだもん!」
「ええっ?!だから俺、全敗だったんすか?!」
気付いてなかったのかよ!と楽しそうな笑い声が響き渡る。鍛錬以外の十一番隊のみんなをちゃんと見るのは、今日が初めてかもしれない。屈強で強面な男性ばかりが集まっている印象だが、実際は良い人ばかりだ。
私は蓮と末席で並んでちびちびお酒を飲んでいたが、池松さんがやっと皆さんとの乾杯が落ち着いた頃を見計らって、私たち二人をまとめて恋次くんが連れていってくれた。
「奏、コイツら新人の佐伯蓮と黒崎。よろしく頼むわ」
恋次くんの紹介で私たちを交互に見やる池松さんは、その後人懐っこい笑顔を浮かべながら、握手を求めて手を伸ばしてくれた。
「『はじめまして』、十三席の池松奏だ。よろしくな」
「佐伯っす。よろしく」
「…よろしくお願いします」
『はじめまして』…確かに蓮はそうかもしれないが、私は違う。初めましてどころか『三度目まして』だ。私はどう反応すれば良いのか分からず、彼の言葉に首を傾げた。すると池松さんは私の疑問に気付いているのか、顔を寄せて耳元で『乱菊さんからお前との現世での繋がりは口止めされてる』と教えてくれた。
*********
「まさかこんな早くに来るとはなー。よく来たな、」
宴会は大盛り上がりで、あちこちで筋肉自慢たちが上半身裸で腕立てやら懸垂やらの勝負をしていて、笑い声が起きている。さすが十一番隊、筋肉バカばかりだ。そんな中、私は池松さんに小さく『聞きたいことがある』と伝えると、彼も察してくれたのか私と蓮を連れて人のいない隅に寄ってくれた。
「…かなり大変でしたけどね」
「そうみてぇだな。俺はちゃんと潤林安の札を渡したのに行ってないんじゃねーかとか責められて、危なく日番谷隊長に殺されるところだったじゃねーかよ」
池松さんはその時のことを思い出しているのか、顔を真っ青にして小さく震える。池松さんにも迷惑をかけてしまっていた。
「その節はどうもご迷惑を…」
「まぁ無事だったなら問題ねーよ。で、お前、やっぱ記憶残ったらしいな」
「うん。池松さんが言ってた通り、信じる者は救われたよ」
私の言葉に池松さんは目を点にして私を見てきた。そして一拍おいて「そうだな」と爆笑する…なんなんだ、一体。
「でも、本当は『信じてたから』とかっていう話じゃないでしょ?じゃなきゃみんな絶対記憶が残っているはずだもの」
そう、これこそ私がずっと池松さんに聞きたかったことー…『何故私の記憶は残ったのか』。誰しもが皆、現世での記憶を残していたいと思うはず。蓮だってきっと覚えていたかったはずだ。飲み会が始まってずっと隣にいてくれる蓮を見やると、彼は池松さんの言葉を待つように、じっと彼を見つめていた。
「そうだな。まぁ、お前は少し他の奴らとは違うってことだ」
「…?」
「んー…あんま詳しいことは言えねぇんだけど、言うなればその『霊力の高さ』が故の力だ。お前ほどの霊力を持っている人間はそういねぇ」
確かに私は現世にいる頃から無駄に霊力が高い。だから冬獅郎にも出会えたし、暴発という形での入隊になってしまったが、現に死神にもなれた。でもそれだけなら、他にも沢山同じような人はいるはずだー…。
「でもー…」
「いいか、覚えておけ。お前のその霊力の高さは『武器』にもなるが、それを悪い方に使おうとすると『脅威』にもなる。誰しもが皆、お前の味方だと思うな」
池松さんは私の言葉を遮り、真剣な表情で話す。『脅威』『味方』…一体何の話だろうか…。首を傾げつつ目の前の池松さんを見ると、池松さんは少し困ったように笑った。
「まぁ…良くわかんねぇよな。つまり、今後何が起きても、俺や日番谷隊長を信じろ」
もっと言えば、それ以外の奴らは全員疑えー…そう真面目に言う池松さんに、私も蓮も息を飲む。よく分からないが、これは恐らく『警告』だ。
「…わかった」
「ん、それでこそだ」
私が頷くと、池松さんはその大きな手で私の頭を撫でてくれた。初めて会った時も思ったが、やはり彼はどこか昔からの知り合いのような接し方をする。そして結局のところ何故記憶が残ったのかは分からないが、このことは何か【大きなこと】が関係している気がした。
しばらくすると頭にあった温もりが突如払われ、それと同時にギュッと頭を抱えられた。
「俺がコイツを守るから心配いらねーよ」
「れ、蓮っ?!痛い痛い痛いっ!」
突然の力強い抱擁に驚き、目の前にある厚い胸板をグイグイ押し返す。蓮の体からはお酒の匂いがプンプンして、相当飲んでいるのがわかる。そのせいか力加減が全然出来ておらず、素直に痛い。
「おっ、日番谷隊長のライバルか!」
「あんな奴ライバルでもなんでもねーよ!」
「けけっ、でけー口叩くのは席官になってからすんだな!」
「痛いよバカ蓮!離して!」
「ほら、離してやれって。さ、難しい話は終いだ。お前らも飲め!」
「あ、は酒弱いんだから飲むな!寄越せ!」
そう言うと池松さんから差し出されたお猪口を奪い、ぐびっと飲まれた。その間も蓮は私を離してくれなくて、肩を抱かれた状態だ。この酔っ払いめ…私はため息をついた。私だって少しくらい飲みたい。
*********
「、大丈夫か…?」
「…ん」
恋次くんが心配そうに私を見てくれているのを視界に捉え、私は小さく頷いた。冬獅郎の言いつけを守り、あまり飲まないでいたー…最初は。途中から【第5回あっち向いてホイ最弱王は誰だ?!】と言う名の、またもやあっち向いてホイ大会(現在十一番隊は【あっち向いてホイ】がブームらしい)が開催され、トーナメント戦で負けた方がお酒を飲むというルールのもと、私は恐ろしいくらい負け続けていた。
最初こそ蓮が代わりに飲んでくれていたが、それはルール違反だと副隊長が騒いだため、意を決して飲み始めたら頭がふわふわして仕方がない。ふと隣を見れば、蓮も酔っているのか赤い顔をしながら、据わった目でじーっと私を見ていた。何さ、文句でもあるのだろうか。
「りぇん、なにさぁ」
「…うるせー。あんまこっちみんな」
そう言って骨ばった大きな手で私の顔を覆う。何をするんだ、見てたのはそっちじゃないか。それにしても、蓮の手は冷たくて気持ちがいい…。お酒のせいで火照った顔に丁度良い温度だ。私はその手を掴むと、おもむろにそのまま頬に当てる。その瞬間、蓮の手が小さく跳ねた気がした。
「りぇん(の手)、きもちいー…」
「っばっ…!お前、何言ってんだよ!」
蓮は焦ったように手を引き、私の頬から離れてしまった。冷たくて気持ちいいと言っただけなのに、何をそんなに怒るのだろうか…。私は意味がわからず首を傾げると、離れた場所で飲んでいたはずの隊員数人がドスドスとすごい音で駆けてきた。
「ちゃん!オ、オレの手もどうぞ!!」
「オレの手も!冷やしてきたから冷たいはずです!!」
「俺なんか今氷握ってるぞ!ギリギリまできんっきん!」
そう言って何本もの手が伸びてきた。冷たければ何でもいいんだけどなぁ…なんて思いつつぼーっと目の前の彼らを見る。そのうちの一本の手に自らのものを重ねようと伸ばすと、奥から何かざわめきが聞こえるのに気付き、ふと止まる。そして次の瞬間には一瞬のうちに、今まで感じたこともないくらいの冷たい空気が部屋中を包み込んでいた。
「お望みならお前ら全員、凍らせてやろうか…?」
「「「?!」」」
「とーしろー?」
目の前の隊員達で姿は見えないが、冬獅郎の声が聞こえる。彼を見ようと立ち上がろうとした…が、お酒が足にまできているのか、縺れて上手く立てない。あ、転ぶ…そう思った瞬間、私の火照った身体は冷たい冷気を纏った体に包まれていた。
「?!」
「…お前、飲んだな」
「…ちょこっとだけだよ」
ジト目で体を支えてくれる彼を見上げると「後で覚えておけよ」と言う言葉と共に、頬を軽く抓られた。頬がジンジンとするが、久し振りに触れる彼の温もりが嬉しくてついにやけてしまう。冬獅郎は私の顔を見るなり驚いた顔をすると小さく「馬鹿野郎…」と言い、素早く私の手を握りそのまま部屋を飛び出した。後ろから乱菊さんの「行け、たいちょー!!」という楽しげな声が響いて思わず振り返ると、彼女は満面の笑みを浮かべて大きく手を振っていた。
........
.....
...
静かな川辺。月と星が綺麗に瞬き、辺りは清らかに流れる川の音と、初秋を告げる虫の音だけが響く。川辺に着くと、店からずっと握っていた彼女の白く細い手を解放する。かなりきつく握っていたらしいその手をそっと外すと、少しだけ淋しさを感じた。
「…冬獅郎?」
小さく聞こえた声に振り向くと、は小首を傾げて見ていた。その瞳は酒のせいもあり少し潤んでいる上、小走りになっていたのか息が切れて頬が赤くなっている。そんな姿に少し申し訳なさを感じつつも、その無防備な姿に額に手を当て俯くと、無意識のうちにため息をついていた。そんな顔して男を見るな、馬鹿野郎…。俺はジト目で彼女を見ると、視線を逸らしそのまま川辺に腰掛ける。も続けて隣に座ったので、俺はその瞬間オレンジ色をわしゃわしゃと思い切りかき混ぜた。
「やめてぇ〜!あたまくゎんくゎんする〜!!」
「うるせー!禁止したのに酒を飲んだ罰だっ!」
そう言いながらサラサラの髪をぐちゃぐちゃにして、満足気に手を離す。は少し涙目になりながら「冬獅郎のバカ…」と言って軽く睨みつつ、手で直し始めていた。その表情に俺はさらに満足し、久しぶりにゆっくりと彼女を眺める。の癖のつきにくい髪はあっという間に戻り、俺が見ていたことに気付いたのか首を傾げてきた。
「冬獅郎?」
「…クマ」
「へ?」
「目の下のクマ、ひでぇぞ」
「何だよ、これ」と言うと右手を伸ばし、彼女の柔らかな頬を包み込む。そして親指で目の下をそっと撫でた。は目を見開き驚いたような顔をしたが、次には困ったような顔をして小さく微笑んだ。クマが出来てしまっている理由は、彼女の口から言う気がないようだ。
「…眠れないなら、前みたいに十番隊に来ればいいじゃねぇか」
俺の言葉には一瞬固まる。そして眉を下げ悲しげな表情を浮かべると、小さく首を振った。
「…行けないよ…」
「なんで?」
「……」
俺の問いかけに、は俯いた。俯いたことで表情は見えないが、俺には彼女がどんな顔をしているのか簡単に想像出来るー…そう、現世にいる頃俺が帰る間際に見せていた、あの淋しげな顔をしているに違いない。俺は小さくため息をつく。そして今度は両手で彼女の頬を包み込むと、ぐいっと顔を上げさせた。
「何に遠慮してるのか知らねーけど、俺はお前一人来たくらいで邪魔だと思わねぇし、仕事に影響もねぇよ」
無理やり上げられた顔は一瞬驚いたような顔をしたが、次にはやはり淋しそうな顔に戻り、口元をキュッときつく結んだ。その予想より遥かに眉尻が下がっていて、見事なハの字具合に思わず笑いそうになる。ほんと、世話のかかるやつだ。そのままの体制で、俺は更に言葉を続けた。
「で、鬼道は?順調か?」
「…うん…」
「嘘つくな。阿散井から『鬼道が苦手で、斬術ばかりに走る傾向がある』って聞いてる」
「…知ってるなら聞かないでよ」
は何かを堪えるかのように下唇を噛み、眉は更に下がる。その表情は、置いていかれた子犬そのものだ。俺は堪えきれず吹き出すと、笑われたことを不思議がる彼女の頬に添えていた手を、そのまま中心にギュッと寄せた。タコのような口元にさらに笑いが込み上げる。
「?!とーしろ?!」
「今まで通り、朝俺が見てやる」
「?!で、でも…」
「『でも』も『だって』もねー」
「いいから、毎朝来い」と、目の前でタコみたいな顔でいる彼女を見ながら伝える。その目には涙が浮かんでいて、何をそこまで拒む必要があるのかと不思議に思う。は相変わらず頬にある俺の手にそっと自身の手を添えると、ゆっくりと頬から離した。そのままキュッと弱く握られると、目線だけを気まずそうに斜め下へ向け、小さく呟いた。
「…本当に迷惑じゃない?冬獅郎にも、十番隊の皆さんにも…」
「迷惑じゃねーよ」
「でも私、十番隊の隊員じゃないよ?隊長の冬獅郎を他隊の、しかも新人の私が独り占めして、いいのかな…」
『独り占め』ー…その小さな呟きに顔に熱は集まるし、何より心臓がキュッと掴まれた気がして、思わず顔を背けた。何可愛いこと言ってんだよ、こいつは…。ちらりと視線だけ目の前の彼女に戻せば、相変わらず例の子犬の表情のまま見てきている。その姿に小さく微笑むと、握られている手の片方だけを話し、頭を小突いた。
「…った…」
「構わねぇよ」
「?」
「俺個人がお前の成長を助けたいから見るんだし、夜も俺個人がお前と話したいから呼んでる。俺とお前の関係に隊長だとか十一番隊だとか、そういうのは関係ねぇだろ」
「それとも迷惑だと思った方がいいのか?」と言うとは頭を下げ、勢いよく首を横に振る。握られている手への力も強まり、言葉に出さずとも彼女の思いが伝わるようで無意識に口元が上がった。
俺は優しく彼女の名を呼ぶ。はゆっくり顔を上げ、涙を浮かべてキラキラ光る目で俺の目を見る。その目をじっと見つめながら、小さく言った。
「俺はお前と、立ち位置とか関係なくこれからも素直に過ごしたい。一緒にいたいと思うから呼ぶし、稽古を見たいから誘う。お前はどうしたい?」
じっと俺の目を見ながら聞いていただが、次第に目からポロポロと涙を零し出す。
「…私も…」
「…ん?」
「私も冬獅郎と、沢山一緒にいたい…!隊は違うけど、稽古もしてほしいし、っく…夜も、今までみたいに、お話したい…!」
「…わかった」
「よく言ったな」と褒めてやると、限界を超えたのかは抱き付いてきて、そのまま大泣きし始めた。そしてそのまま俺とあまり過ごさなかった三日間の話を沢山して、いつだかの夜のように安心しきった顔で眠ってしまった。
この数日で彼女に何があったのかは分からない。だがやはり、他の隊の隊長である俺にかなり遠慮の気持ちを持っていたように感じる。たった三日ではあるが、離れていたこの数日で改めての存在の大きさを実感した。
ふと腕の中にいる彼女を見ると、どこかスッキリしたような印象だ。ほんとめんどくさいヤツ…そう思いつつもやはり可愛いコイツのことは憎めなくて、スヤスヤ眠る彼女の額に小さく口付ける。そしてその小さな体を大事に抱えあげると、数日前まで当たり前のように一緒に夜を過ごしていた十番隊の執務室へ向かった。